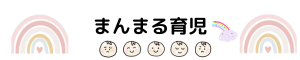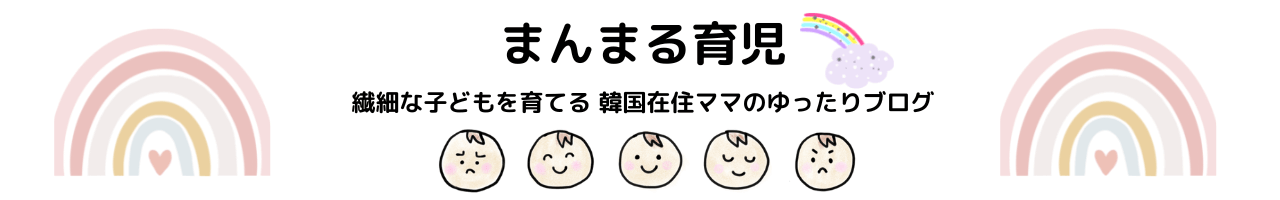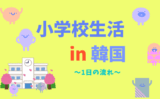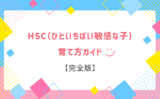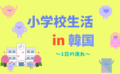HSC(ひといちばい敏感な子)である息子が小学校に入学して2ヵ月。
「ちゃんと通えるだろうか」「行き渋りは起きるのでは?」と、ずっと心配してきました。
結果は──登校しぶりは一度もなし!
「毎日疲れるけど楽しい!」と話してくれて、親としてはホッとしています。
登校しぶりがなかった理由
保育園時代、最後まで苦労したのがお昼寝。
必ず横にならなければいけない時間が息子には大きなストレスでした。
だからこそ「お昼寝から解放されたこと」や給食が美味しいというのも、
学校が楽しいと感じる大きな理由のひとつだったようです。
入学後に見られたサイン
順調に見えても、HSCならではの反応は出ていました。
「外ではいい子」でいる分、家に帰ると心身の疲れが一気に出ていたのだと思います。
他の子たちは、学校生活に加えて習い事もたくさんしていますが、
息子は早々に帰宅し、しっかり休んで翌日に備えます。
親として工夫したこと
周囲からは「過保護」と思われるかもしれませんが、安心して通えることが最優先。
まずは「毎日通う」ことを目標にしました。なったのもストレスなのかもしれません。
追記:入学から1年半が経って
「学校に行きたくない」と言ったことは一度もなく、友だちとの関わりも増え、発表の場にも挑戦するようになりました。
HSCの息子にとって、ここまで“毎日学校に通えている”こと自体が大きな成長だと思います。
ただし現実には、長期連休明けの新学期には数週間ほど行き渋りが出るのも事実です。
2年生の夏休みは、行き渋り対策も兼ねて、できるだけ毎日学校の活動に参加して忙しく過ごしました。
それでもやはり休み明けには、学校の門の前で「いやだなぁ~…」とつぶやきながら教室に向かいます。
どんな工夫をしても「繊細さ」そのものは変わりません。
だからこそ、焦らず・比べず・見守ることが大切だと感じています。
改めて思うのは、HSCの子にとって「安心して通えること」が成長の土台になるということ。
その安心感があるからこそ、時間をかけながら少しずつ前に進んでいけるのだと実感しています。
まとめ
入学直後は母子登校や癇癪に悩みましたが、2ヵ月、1年と過ごすうちに、息子は確実に成長しています。
HSCの子には「完璧な環境」よりも「安心できる環境」が何より大切。
小さな一歩を積み重ねる日々の中で、息子なりの成長を見守っていきたいと思います。