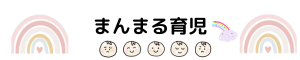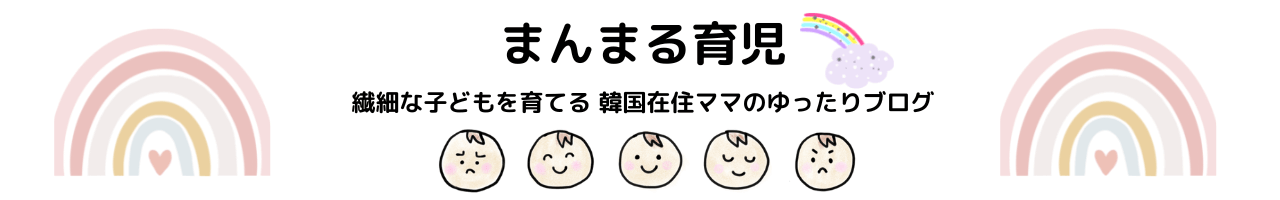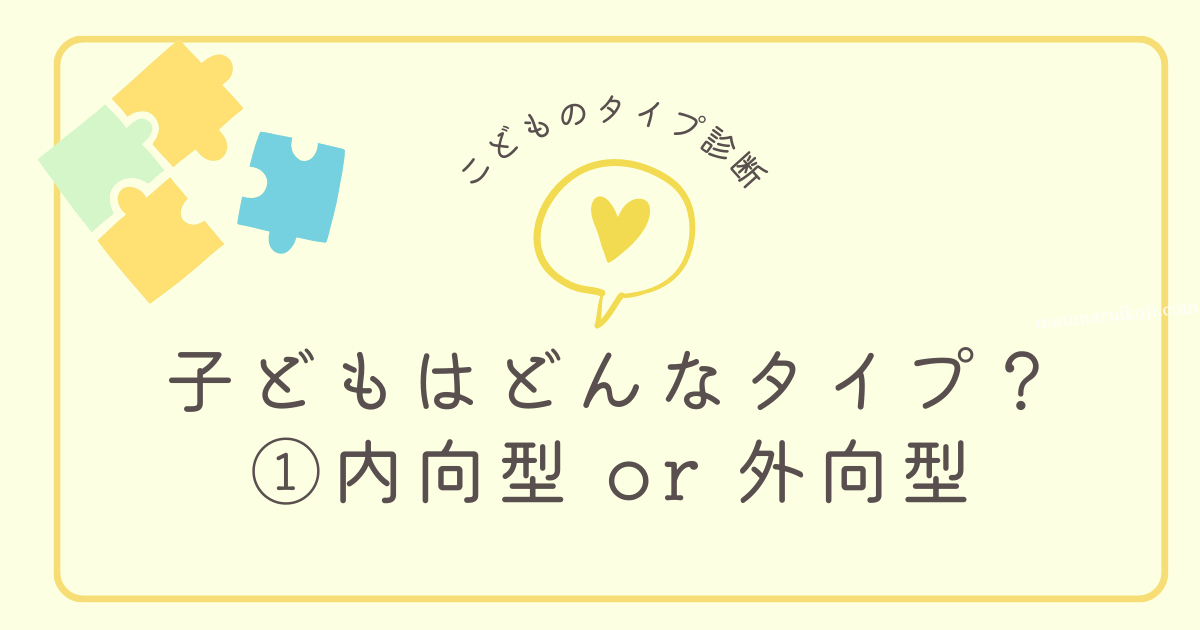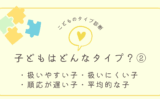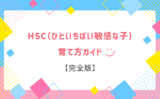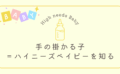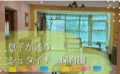こんにちは。繊細なお子さんと向き合うママ・パパのみなさん、いつも本当におつかれさまです。
「うちの子って、どんなタイプなんだろう?」
そんなふうに思ったこと、ありませんか?
同じ兄弟でも性格がまったく違って、不思議に感じることってありますよね。
私の息子は、赤ちゃんの頃からよく泣く子で、とても手がかかりました。
「どうしてこんなにグズるんだろう?」と疑問に思い、赤ちゃんでも受けられる“気質診断”を調べてみたんです。
今回はその経験をもとに、「内向型」「外向型」といった子どもの気質を見分けるヒントをご紹介します。
お子さんの成長の見通しにも役立つ内容ですので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
子どもの気質を知ることの大切さ
子どもには、一人ひとり異なる個性があります。
手のかからない子もいれば、よく泣いて親を悩ませる子もいます。
でも、手がかかるからといって「ダメな子」なんてことはありません。
それは、その子が生まれ持った“気質”の違いによるものなのです。
人見知りで泣きやすい子もいれば、誰にでもニコニコと笑顔を見せる子もいます。
特に赤ちゃんの頃は、気質がそのまま“性格”のように見える時期なので、戸惑うこともあるかもしれませんね。
心理学では、気質と環境の両方が子どもの人格形成に影響すると考えられています。(おおよそ気質50%、環境50%)
「こんなふうに育ってほしいな」という願いがあるなら、まずはお子さんの気質を知り、理解することがとても大切です。
とくに育児に悩んでいるときには、
「もしかすると、この子は“感じ方”が少し違うのかも?」と視点を変えてみることで、
接し方のヒントや、子育ての糸口が見えてくるかもしれません。
「内向型・外向型」診断
アメリカの心理学者・ケーガン博士の研究では、生後4ヶ月の赤ちゃんにさまざまな刺激を与え、その反応の仕方から生まれ持った気質を見極めようとしました。
この診断のポイントは、“恐怖や不安への反応”に注目している点です。
ケーガン博士の実験では、以下のような刺激を赤ちゃんに与え、反応を観察しました。
これらの刺激に対する反応の強さによって、赤ちゃんは以下の3つのタイプに分類されました。
刺激に敏感な赤ちゃん(高反応タイプ)
刺激に鈍感な赤ちゃん(低反応タイプ)
中間タイプ
私の息子の場合、生まれたときからとても刺激に敏感で、他の赤ちゃんと比べてもよく泣き、反応も強めでした。
このような特性から、私は彼の気質を「内向型」だと捉えています。
さて、ここで注目すべきはこの気質が成長しても持続する傾向があるという点です。
ケーガン博士によれば、赤ちゃんの頃に見られた気質はその後の成長段階でも比較的一貫しており、
つまり、赤ちゃんの気質は成長とともに変わるというよりも、その子の「基本的な感じ方・反応の仕方」として持続しやすいということですね。本的には大きく変わりにくいということですね。
幼少期〜児童期の「内向型」「外向型」の特徴
では、少し成長したあとの内向型・外向型の特徴を比較してみましょう。
※ポイントは、「新しい環境・人・物事への適応性」です。
内向型(行動的抑制が強いタイプ)
外向型(行動的抑制が弱いタイプ)
こうして見比べてみると、内向型は控えめで消極的に見える一方、
外向型のほうが積極的で「育てやすそう」と思われがちかもしれません。
しかし実は——
このあとに続くように、内向型にも外向型にも、それぞれにかけがえのない魅力があるのです。強みがあるのです。
子どもの気質の変化
その後、1歳9ヶ月〜7歳6ヶ月の子どもたちを対象にした追跡研究でも、興味深い結果が報告されています。
これは生後4ヶ月時点の調査結果とほぼ一致しており、大きな変化は見られないように思われます。
一方で、7歳半の時点で、約4人に1人(約25%)の子どもが「内向型の特徴を示さなくなった」とのことです。
気質は変わる?育て方と環境の影響
この結果からわかるのは、気質は生まれつきのものではあるものの、「完全に固定されたもの」ではないということです。
つまり、育て方・環境・経験などによって、ある程度は変化する可能性があるのです。
この研究が行われたアメリカでは、文化的に「外向的な性格」が好まれる傾向があります。
自己主張ができること、社交的であることが評価される場面が多く、自然と親たちもそれに沿った育て方をする傾向があるようです。
そのような背景から、もともと内向的だった子どもが、外向的な環境の中で少しずつ行動のパターンを変えていくこともあるのかもしれません。
日本の文化との違いと配慮
一方、日本では協調性や「空気を読む力」が重視される文化があります。
そのため、内向的な子どもが自然に受け入れられやすい社会的風土があるとも言えるでしょう。
しかしながら、その裏で、他人に配慮しすぎるあまり、自分の気持ちをうまく主張できないまま成長してしまうリスクもあります。
だからこそ、内向的な子どもほど、「安心して自分の意見を伝えられる環境」を整えてあげることが大切だと感じます。
小さな自己主張や表現を丁寧に受けとめ、自己肯定感を育てることが、その子らしさを守り伸ばす土台になるのではないでしょうか。

内向型・外向型、それぞれの魅力
人にはそれぞれ異なる気質があり、内向型にも外向型にも、かけがえのない魅力があります。
内向型の魅力
外向型の魅力
どちらの気質にも、それぞれに素晴らしい特性があります。
たとえば、内向型の子どもは、観察力や分析力に優れ、じっくり考えてから行動するタイプです。
一方、外向型の子どもは、新しいことに臆することなく、積極的にチャレンジできる傾向があります。
両方の特性をバランスよく持っていたら……まさに理想的ですね(笑)。
外向型は“目立ちやすく、評価されやすい”?
個人的な印象ですが、子どもの頃は外向型の子のほうが、まわりから好意的に受け取られやすい場面が多いように感じます。
誰にでも挨拶ができ、新しい場所にもすぐ馴染める。
笑顔が多くて愛嬌たっぷりだと、「子どもらしくて可愛い!」といった印象を持たれることも多いですよね。
私だったら、お菓子をあげたくなっちゃうかな~(笑)
息子の場合
私の息子は完全に内向型タイプ。
人見知りが強く、挨拶も苦手。外でニコニコするのもあまり得意ではありません。(家とは別人・・)
新しい環境に慣れるまでに時間がかかるため、正直「もっと自分を出せたらいいのに」と思うこともあります。
それでも、思慮深くてやさしい性格は、敵を作りにくく、まわりの人から好かれやすいですし、慎重なおかげで危ない行動が少ないという内向型ならではの良さも、日々感じています。
このように、どちらの気質もそれぞれに強みがあり、「どちらが良い・悪い」といったものではありません。
大切なのは、その子らしいあり方を理解し、無理に型にはめようとせずに自然な成長を見守ることだと感じます。
さいごに
私自身も、息子と同じく内向型の人間です。
幼いころから外では静かで控えめな子どもでしたが、「これがやりたい」と思ったことに対しては、意外と行動的で、しっかり主張するタイプでもありました。
もちろん、くよくよと悩むこともありましたが、今では内向的であることも「私らしさ」のひとつとして受け入れられるようになっています。
赤ちゃんの頃の息子は、不安なことがあるとすぐに泣いてしまい、毎日「抱っこ、抱っこ」の繰り返しでした。
そんな日々を経て、今ではHSC(ひといちばい敏感な子)としてすくすく育ち、小学生になりました。
ただ、内向型の気質も、度が過ぎると社会の中で生きづらさを感じる場面が出てくることもあります。
だからこそ私は、できるだけ早い段階で「この子の気質」を理解し、安心できる環境を整えてあげたいと考えるようになり、海外での生活を選びました。
穏やかな空間を大切にするシュタイナー保育園に通わせ、そこから少人数の小学校へ。
「この子にとって、安心できる場所はどこだろう?」と考えながら、少しずつ環境を選んできました。
子どもだからこそ、今は「まだ許される」こともたくさんあります。
これからいろいろな経験を積みながら、少しずつバランスを覚えていってくれたら——
そんなふうに、ゆっくりと、見守っていきたいと思っています。