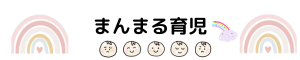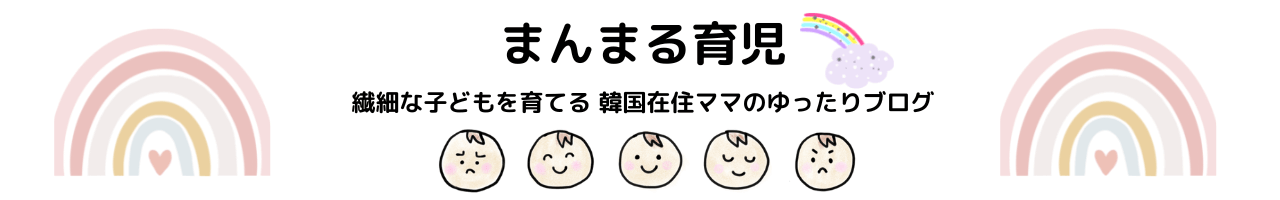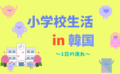韓国の小学校に入学してすぐ、いちばん驚いたのが「放課後の長さ」でした。
うちの息子も、授業が終わるのは13時半ごろ。
朝送ったと思ったら、すぐ迎えの時間。
思わず時計を二度見…という日々のスタートでした(笑)
「このあと、どう過ごせばいいの?」
そんな悩みに応えてくれるのが、韓国ならではの放課後サポート制度。
塾に行く子も多いけれど、教育費が気になるのが親心。
ありがたいことに、学校でもいろいろなプログラムを用意してくれていて、
学童っぽい「トルボム」、安く習い事ができる「パンガフ」、
そして最近スタートした「ヌルボム学校」など、選択肢もさまざまです。
この記事では、韓国の小学生たちの放課後の過ごし方について、
親目線で感じたことや、実際に使ってみた制度の体験談も交えながらご紹介していきます。
✏️ 韓国小学生の放課後、選択肢は主に3つ!
① 学習塾や習い事に通う
学校が終わると、そのまま塾へ直行!という子も多め。
国語・英語・数学などの学習塾のほか、ピアノやテコンドー、水泳なども人気です。
ちなみに、韓国の習い事の多くはスクールバスで学校前までお迎えに来てくれるので、親が送迎しなくていいのは本当に助かります。
帰りも家の前で降ろしてくれる場合が多く、送り迎えに追われることがないのが◎。
② パンガフ(방과후)=放課後プログラム
学校の中で行われている、選択制の習い事のような活動です。
希望する子だけが申し込み、好きな講座を受講できます。
内容は学校によってさまざまですが、たとえば:
費用は安価で、1講座3か月で約8,000円(教材費別)ほど。
外部講師を招いているので内容もしっかりしていますし、学校内で完結するので送り迎えも不要です。
③ トルボム(돌봄)=学童保育
いわゆる日本の「学童」に近い制度です。
特に1・2年生など、まだ一人で過ごすのが難しい年齢の子どもたちを対象に、授業後〜夕方まで学校で預かってくれます。
人気のある学校では抽選になることも。
また、高学年になると放課後の時間が短くなるため、主に低学年向けのサポートとして活用されています。
うちの息子は学童(トルボム)に通っていなかったので、代わりにパンガフをフル活用!
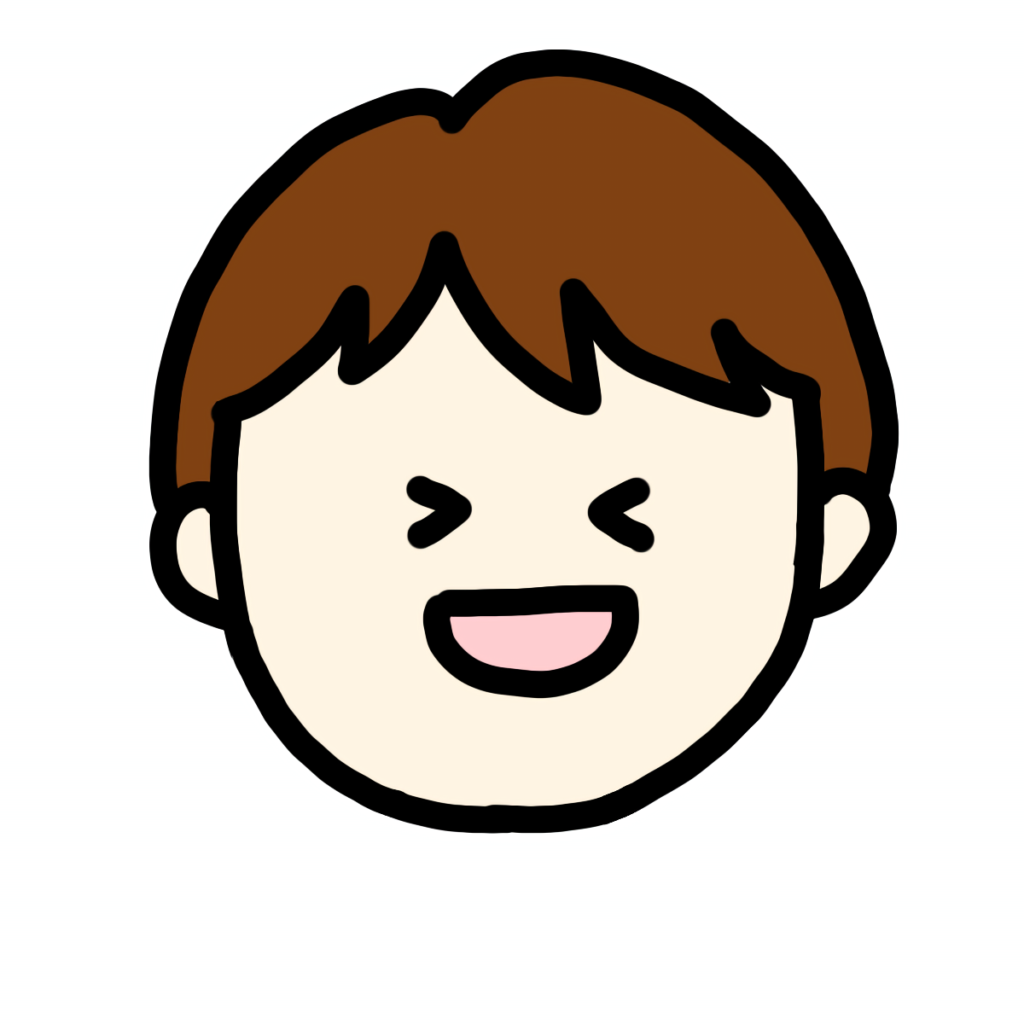
ぼく、ロボットつくりたい!
うんどうもしたい!
そんな希望を聞いて、5つの講座に申し込みました。
学校の中で完結するから、授業が終わったらそのままパンガフへ直行。
自然と「今日は○○の時間だ〜♪」と楽しみにするようになり、私としても下校時間が伸びて本当に助かっています。
さらに最近では、希望者全員が利用できる新制度ヌルボム学校もスタートし、
学校によってはより選択肢が広がってきました。
わが家も、放課後の過ごし方を工夫しながら「無理なく・楽しく」学校生活を送っています😊
🆕 ヌルボム学校ってどんな制度?
2024年から一部の小学校で始まった「ヌルボム学校(늘봄학교)」は、
トルボム(学童)に近い仕組みですが、無料で“学び”の時間が確保できる放課後制度です。
✏️ ヌルボムのポイント
うちの学校も対象だったので、さっそく申し込みました。
ただし「学童(トルボム)を利用している子は参加できない」という決まりがあり、
希望したのはなんと息子ひとりだけ。
その結果、まさかの先生とマンツーマンでのヌルボムがスタート(苦笑)
週2回、静かな教室で先生と2人、ちょっと特別な放課後を過ごしています。
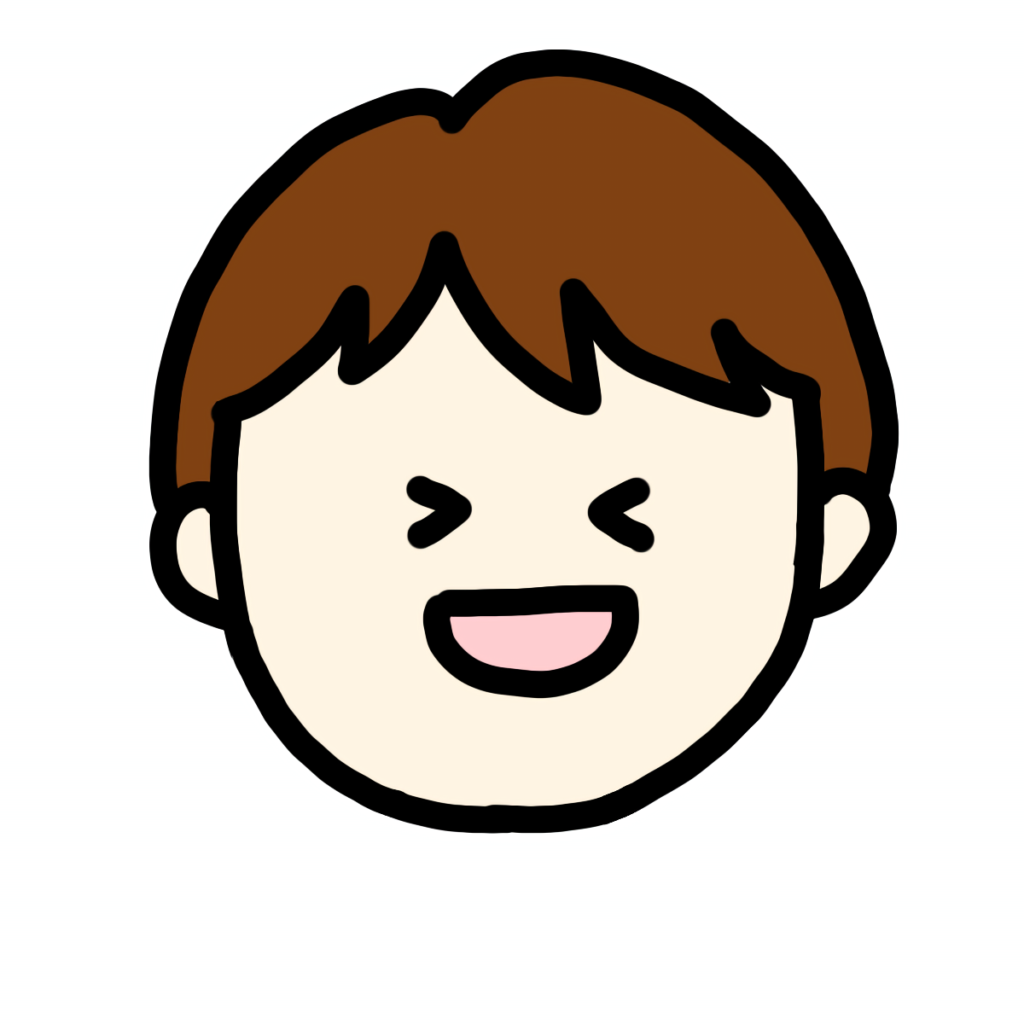
ピアノが弾けるようになった!
運動や勉強の日もあるよ
ちなみに、ヌルボムが始まる前は
「給食後に一度帰宅 → パンガフの時間に再登校」という非効率なスケジュールになる日もあって、
この“スキマ時間”が埋まったのが本当にありがたかったです。
共働き家庭だけでなく、どの家庭でも使えるというのもヌルボムの魅力ですね。
🎒 年齢別・放課後の過ごし方の変化
韓国の小学生は、学年が上がるごとに放課後の過ごし方が変わっていきます。
「遊び」から「学び」へ——そのシフトがとてもはっきりしています。
🧸 1〜2年生
学校でそのまま活動できるので、送り迎えの手間がないのが◎
📘 3〜4年生
放課後の使い方に“個性”が出てくる時期。
✏️ 5〜6年生
本格的な“勉強モード”へ。放課後も時間割のように動く日々
このように、韓国では学年ごとに放課後の過ごし方が大きく変わっていきます。
その時々の子どもの様子を見ながら、無理なく続けられるスタイルを選ぶのがポイント。
とはいえ、高学年になっても、子どもたちは自分の“好き”をあきらめたわけではなく、
勉強とのバランスを取りながら、パンガフなどをうまく活用して趣味や興味を続けている子も多い印象です。
✅ さいごに
韓国の小学生の放課後について、わが家の体験も交えながらご紹介しました。
最初は「授業、もう終わり!?」「午後、どうしよう…?」と戸惑うことも多かったですが、
実際に制度を使ってみると、思った以上に選択肢があって、親子ともに助けられる場面がたくさんありました。
特に、学校内で完結する放課後のプログラムは、子どもの興味を伸ばしつつ、
親の負担も軽くしてくれる、ありがたい存在です。
これから学年が上がるにつれて、また放課後の過ごし方も変わっていくと思いますが、
子どものペースに合わせながら、無理なく・楽しく見守っていけたらと思っています。
韓国の小学校生活や子育てに興味がある方にとって、
少しでも参考になる内容になっていたら嬉しいです🌱