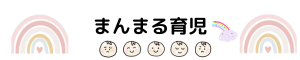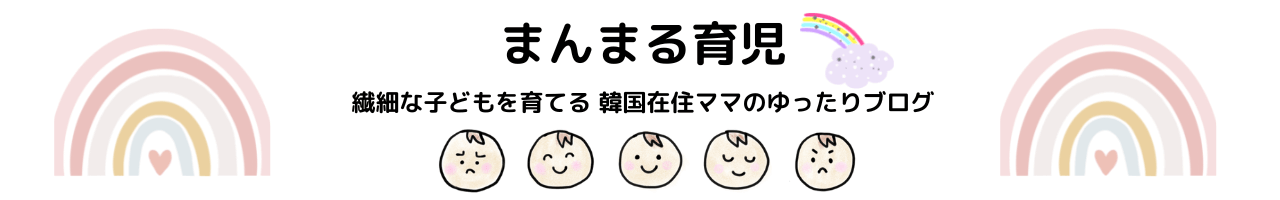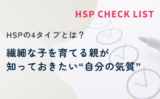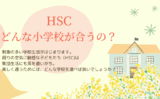HSC(ひといちばい敏感な子)の息子にとって、新しい環境に慣れることはとても大きな負担です。
保育園時代の登園しぶりを通じて、「毎日通えることは当たり前ではない」と痛感しました。
だからこそ小学校は、できる限り穏やかで少人数の学校を選びたい──そう考え、通学可能な範囲で「小さな学校」を探してきました。
最終候補に残ったのは、
冬にそれぞれの入学前説明会に参加し、実際に見聞きしたことや、わが家の決断についてまとめます。
シュタイナー小学校の説明会で感じたこと
シュタイナー学校は、試験も教科書もなく、暗記よりも芸術や体験を重視する独自の教育方針を持っています。
魅力
課題
説明会では「卒業後の進路」に関する質問が多く出ていました。
芸術の道に進む子もいれば、一般企業に入る子もいるそうですが、親としては将来の不安がぬぐえません。
北米やヨーロッパでは制度が整っている国もありますが、アジア圏では経済的・制度的に壁が大きいのが現実だと感じました。
公立小規模校の説明会に参加して
12月、学区外にある公立小規模校の説明会に参加しました。
参加したのは数家族で、先生の数のほうが多いほどでした。
他の家庭も「大規模校を避けたい」という理由で来ていて、共通の思いを感じました。
印象に残った点
説明を聞きながら、保育園時代の縦割り保育に似た温かさを感じ、「ここなら息子に合う」と思えました。
学区外入学の制度と注意点(韓国の場合)
今回の公立小学校は学区外のため、日本同様に「指定校変更」の手続きが必要でした。
地域や自治体によってルールが異なるため、必ず事前に問い合わせて確認しておくことが大切だと感じました。
わが家の決断
当初は「シュタイナー教育しかない」と思っていました。
しかし現実的には、学費・資格・通学・家庭での努力の面でハードルが高すぎると判断。
一方で、公立の小規模校でも息子が安心して通える環境は十分に得られると感じました。
そして、最終的にわが家は、「小規模の公立小学校」 を選ぶことにしました。
まとめ
HSCの子どもにとって「安心して通える環境」は何より大切です。
教育方針や特色も大事ですが、制度や現実的な条件を踏まえて、家庭に合った選択をすることが欠かせないと感じました。
完璧な学校はありません。
それでも「子どもが安心して通える場所」を基準に選んだ今回の決断には、今も納得しています。