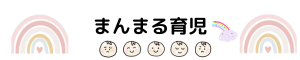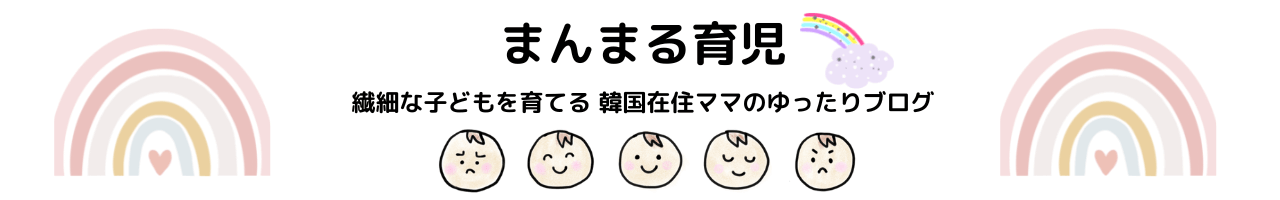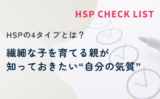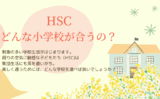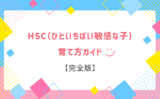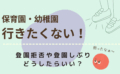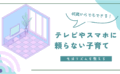こんにちは。
我が家の息子はHSC(ひといちばい敏感な子)で、幼い頃から環境の変化にとても時間がかかるタイプでした。
保育園も少人数で穏やかなリズムのシュタイナー教育の場を選びましたが、それでも慣れるまでには1年以上。
週明けには今でも登園を渋り、時には泣き声で朝が始まることもあります。
そんな息子がいよいよ小学校へ。
「どんな環境なら安心して通えるのか」
これは我が家にとって大きなテーマでした。
学区の小学校を見に行ってみて
まず考えたのは、学区内にある公立小学校。
1学年2クラス、1クラス20人前後という人数は、周辺の学校と比べても少ないと言える規模です。
運動や遊びにも力を入れていて、学校全体の雰囲気もとても良い印象でした。
ただ、息子にとってはその人数ですら負担になるのでは…という不安が拭えませんでした。
彼は周りの人の表情や声のトーンにすぐ気づき、それが気になって集中できなくなることがあるからです。
「みんなと同じペースで活動すること」にどこまでついていけるのか、正直心配でした。
偶然見つけた小規模校
そんなとき、徒歩圏内にある「超小規模な公立小学校」の存在を知りました。
1学年に1クラス、しかも10人前後。
歴史のある学校で、今では新しくできたマンモス校の影にひっそりと建っています。
初めてその学校を見たとき、思わず「ここなら…!」と声が出そうになったのを覚えています。
人数・距離・雰囲気、そのすべてが息子に合いそうだと直感しました。
惹かれた理由と残る不安
自宅から少し距離はあったけれど、一度息子と見に行くことにしました。
学校に近づくと、こぢんまりとした校舎に子どもたちの声が響き、先生と生徒が近い距離でやり取りしている姿がありました。
「ここなら、息子の小さな変化にもすぐ気づいてもらえそう」
そんな安心感がありました。
人数が少ない分、発表や行事の場面でも自然と全員に出番があるでしょう。
大人数だと「埋もれてしまう」タイプの息子にとって、少しずつ挑戦を積み重ねられる環境はプラスになると感じました。
一方で、小規模ならではの不安もありました。
実際、保育園の先生から「この学校は数年後に近隣の大きな学校と合併する話が出ているんじゃない?」と聞いたことがありました。
「せっかく慣れても転校になったら…」と考えると、気持ちが揺れる時期もありました。
韓国での学校探しはチーム作業
我が家は韓国で暮らしているため勝手がよく分からず、学校探しは正直苦労しました。
私は韓国語が得意ではないので、まずはインターネットでリサーチし、出てきた情報を夫に共有。
夫が改めて詳細を調べたり、学校に直接問い合わせたりしてくれました。
学校探しは完全に「夫婦のチーム作業」だったと思います。
リアルな声に助けられた
一番参考になったのは、やはり身近な人からの情報です。
保育園には学校で働く先生のママ・パパも多く、実際の雰囲気を聞かせてもらえたのは本当にありがたいことでした。
ある日、お迎えに来ていたパパさんに思い切って声をかけたところ、普段は無口な方なのにとても丁寧に、近隣の小規模校の様子や入学準備について教えてくださいました。
あのときの情報がなければ、いまのように前向きに決断できていなかったと思います。
良い情報は、意外なところに転がっているもの。
自分から動いて話してみることで、学校探しの大きなヒントが得られました。
最終的な決め手
それでも最終的に「ここにしよう」と思えたのは、やはり 息子の安心感を最優先にしたい という気持ちでした。
学校は毎日通う場所。
「今日も大丈夫」と思える環境でスタートできれば、息子なりのペースで成長していけるはずです。
完璧な学校はないと分かっていても、いまの息子にとって一番安心できる場所を選ぶことが、親としてできることだと考えました。
さいごに
小規模校を選んだ背景には、HSCの子を育てる親ならではの不安や葛藤がありました。
もちろん、人によっては「友だちをたくさん作ってほしい」と大規模校を選ぶのも自然なことだと思います。
でも、我が家にとっては「まず毎日通えること」が目標。
そのために、息子にとって安心できる小さな学校を選んだのは、いまでも納得できる選択です。
HSCの子に合う学校は一つではありません。
わが家の体験が、これから学校探しをする方のヒントになれば嬉しいです。