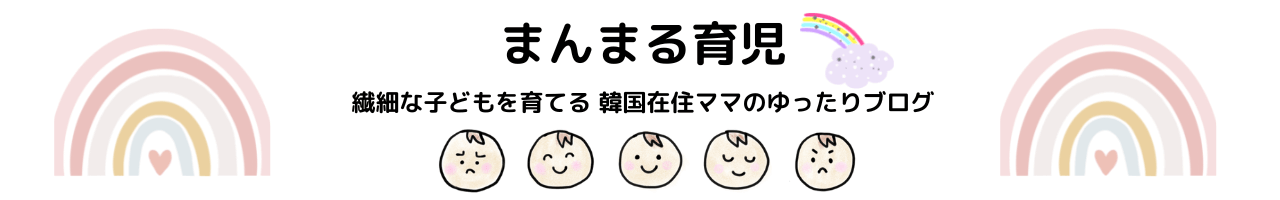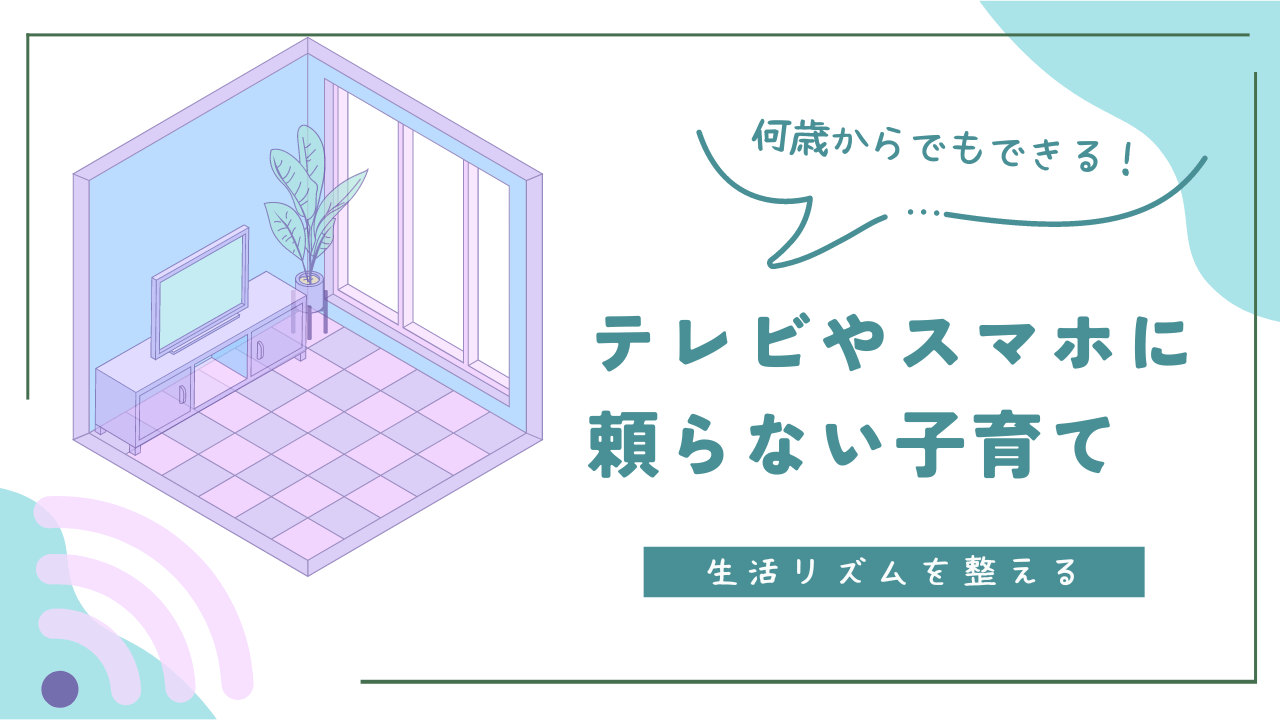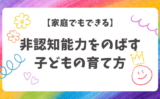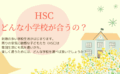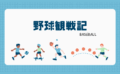3歳から始めた“テレビ・スマホなし育児”のリアルとは?
現実的な工夫や子どもの変化を、等身大で紹介します。
はじめに:テレビなし育児、現実的にできるの?
「2歳未満の子どもにはテレビを見せない方がいい」——そう言われても、実際にはなかなか難しいものですよね。
家事に追われているとき、子どもがぐずってどうしようもないとき、ついスマホやYouTubeに頼ってしまう。私もまさにそうでした。
そんなわが家が、あるきっかけから息子が3歳のときに“テレビ・スマホに頼らない育児”を始めることに。
教育熱心なわけでも、ストイックでもありません。
でも、始めてみると、思っていた以上に子どもにも、親にも“変化”がありました。
今回はそのリアルな体験談を、「ちょっと試してみようかな」と思っている方にも読みやすくご紹介します。
きっかけは保育園。シュタイナー教育で「テレビなし」へ
我が家がテレビを手放すことになったのは、息子がシュタイナー教育を取り入れた保育園に通い始めたのがきっかけでした。
園の方針で「メディア(テレビ・スマホ・タブレットなど)を避ける」必要があり、我が家も半ば強制的に“テレビ断ち生活”へ突入することに。
最初に戸惑ったのは、子どもではなく私自身。
「テレビのない生活なんて無理かも…」という不安からのスタートでした。
メディア断ちの背景:シュタイナー教育ってこんな感じ
息子の通う保育園では、テレビやスマホはもちろん、音楽やラジオなどの“ながらメディア”も基本NG。
最初は正直「そこまで!?」と驚きましたが、園が取り入れているシュタイナー教育の方針によるものでした。
この教育スタイル、ざっくり言うと「昔ながらの、シンプルで自然な暮らし」を大事にするんですね。
デジタルに頼らず、子どもの感性や想像力をできるだけ自然な形で育てていこうという考え方です。
特徴的なのが、キャラクターものの持ち物がNGなこと。
バッグや水筒、お弁当箱、服の柄まで、なるべくシンプルな素材のものを選ぶようにしています。
理由は、キャラクターのイメージが強すぎると、子どもの想像の余地がなくなってしまうからだそう。
園の先生がこんなことを話してくれました。
「子どもって、一度にひとつのことしか集中できないんですよ。だからこそ、余計な音や映像がない静かな環境が大事なんです。」
たしかに、大人でもテレビをつけっぱなしにしてると、なんとなく気が散りますよね。
そう思うと、「静けさとシンプルな遊び」って、意外と贅沢な環境かもしれません。
テレビを消して変わった7つのこと
テレビを手放すなんて無理かも…と思っていましたが、実際に始めてみると息子には明らかな変化がありました。
とくに感じたのは、こんな7つのことです。
「本好きになる!」みたいな魔法は起きませんでした(笑)。
それよりも、6歳までのあいだにしっかり生活リズムを整えたことが、息子にとって“これからを生きるための土台”になっている気がしています。
「テレビなし」育児のポイント
「うちでもやってみようかな?」と思った方のために、わが家で実践している工夫やコツをまとめてみました。
わが家流・テレビなし育児のすすめ方
いちばん大切なのは、「他の家庭と比べないこと」。
自分たちに合ったペースで、ムリなく続けられる方法を見つけていけたら十分です。
工夫:テレビがあっても“見せない空間”に
「テレビを撤去まではちょっと…」という場合は、カバーをかけて視界から消すのが効果的。
子どもは目に入ったものに自然と興味を示すため、テレビやお菓子、おもちゃなども、必要ないときは“隠す”のがコツです。

注意点:イヤイヤ期は特に慎重に
テレビやスマホを一度見せてしまうと「なんで今日はダメ?」と混乱しやすく、依存も強まりがちです。
また、CMやキャラクターの影響で「これ欲しい!」「それ買って!」と物欲が刺激されやすくなることも。
逆に言えば、テレビを見せなければ、たとえ名前は知っていても、そこまで強い関心を持たずに済みます。(お友達がハマっている場合は難しいかもですが)
わが家では、こうした制限を「ダメ!」と頭ごなしに否定するのではなく、
「他にも楽しいことがたくさんあるよ」と、できるだけ肯定的な言葉で伝えるようにしています。
とはいえ、もちろん毎日うまくいくわけではありません。
気分によっては「見たい!」「嫌だ!」と泣かれることもあるでしょう。
そんなときのために、私は子どもがワクワクしそうな遊びやアイディアを、あらかじめストックしておくようにしています。
そして、「今だ!」というタイミングで、それをポンっと差し出す。感情を受け止めながら、「楽しい気持ち」にそっとスライドさせてあげるようなイメージです。

“未完成”なおもちゃが想像力を育む
わが家では、「木のおもちゃ」や「積み木」など、自由度の高い“未完成なおもちゃ”を意識的に取り入れています。
完成された機能やルールがあるおもちゃよりも、子どもが自分の発想で遊び方を見つけていけるものの方が、想像力が育つと教えてもらったからです。
特にお気に入りなのが、シュタイナー園でも使われていた「アーチレインボー」。
半円型の木製パーツを自由に重ねたり並べたりして、橋・山・トンネル・おうちなど、子どもたちが毎回違うものを作り出しています。
たしかに価格はちょっと高めですが、
わが家では「おもちゃの数は少なく、そのぶん“長く使えるものを選ぶ」というスタイル。結果的に、長く使えてコスパも◎でした。
親にとっても、試される育児スタイル
「テレビなし育児」は、正直なところ…親も大変です。
私も何度も「ひとり時間が欲しい…!」と、心の中で叫んでいました(笑)
でも、夫と協力しながら少しずつ形にしてきました。
映画好きの夫も、しばらくは封印(笑)
“6歳までの辛抱”と割り切って、ふたりでがんばっています。
幼児期だけの「制限」だからこそ意味がある
我が家では、「テレビなし」は幼児期限定と決めています。
小学生になれば、テレビやゲームの話題についていく場面もあるでしょう。
その時は、「ルールを守って見る」ことを教えていけたらと思っています。
最近では、CMのない動画配信サービスなどもあり、選び方次第で良質なコンテンツとの出会いもありますよね。
休日どうする?家事はどうする?
テレビがないと、雨の日や家事中、困ることもありますよね。
我が家では「とりあえず外に出る」をルールにしています。
朝から近所を散歩したり、公園で身体を動かしたり。外の空気は最高のリフレッシュです。
家事も子どもと一緒に「遊びにしてしまう」のがコツ。
「お手伝いしようね」ではなく、
「今日は〇〇をやって、おうちをピカピカにしよう!」と、“家族の一員”として任せるようにしています。
「テレビを使わない=ガマン」ではなく、
暮らしの中で楽しみを見つける工夫が、わが家の毎日を支えています。

おわりに:正解はひとつじゃないから
子育てって、「こうすべき」「これはダメ」と言われがちだけど、
本当に大事なのは、それぞれの家庭に合った“ちょうどいい距離感”を見つけることだと思います。
「テレビやスマホって、本当に必要?」
「どれくらいならOK?」
——そんな問いに、明確な正解はありません。
わが家は、保育園の方針に合わせて必死にやってきただけ。
しかも息子は我が強くて、いったん見せたら絶対にケンカになる…そんなタイプだったからこそ、徹底的にテレビやスマホと距離を置く選択をしました。
でも、これはあくまでわが家のスタイル。
うまくいかない日もあるし、無理はしていません。
「今日は一緒に掃除できたらラッキー♪」
そんなくらいの気持ちで、ゆるく、でも工夫を忘れずに。
日々の小さな積み重ねが、心地よい育児につながっていくと信じています。