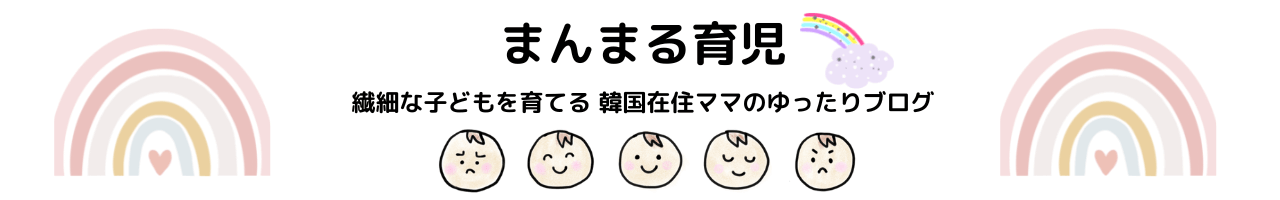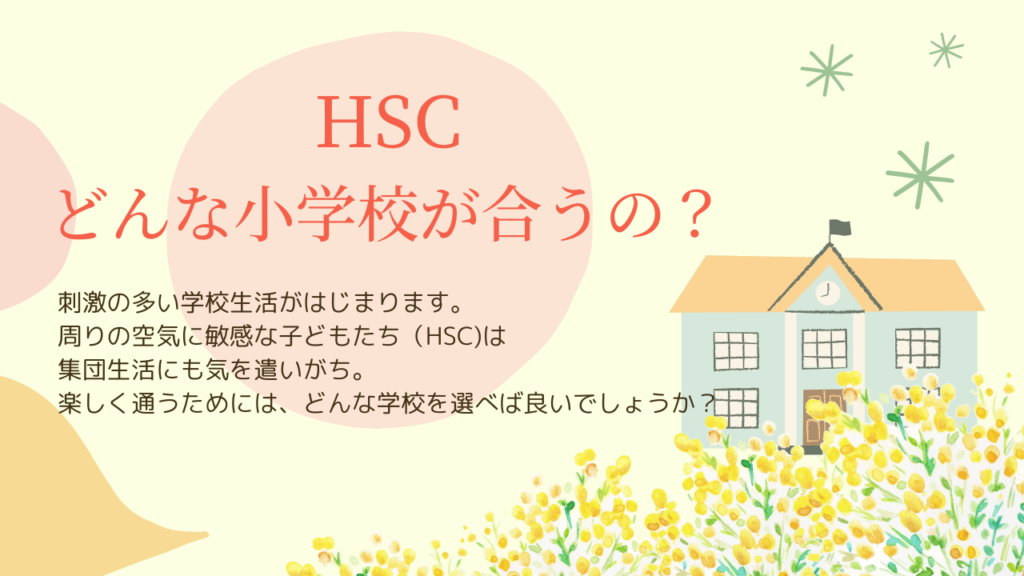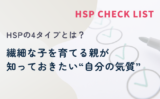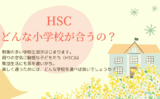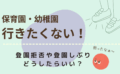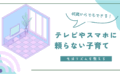こんにちは〜!
韓国ではすっかり秋の風が心地よくなってきました。
先週からは30度を超えることもなく、日陰に入るとひんやりしていて、ようやく秋を実感できる気候です。
セミの鳴き声が聞こえなくなったこの頃ですが、我が家では今朝も、年長の息子の泣き声が元気に響いていました。
週明けになると登園を渋る姿は変わらず。繊細な性格ゆえ、切り替えに少し時間がかかります。
そんな息子が来年から通う小学校をどうするか。
これまでずっと悩んできたのですが、家族でたくさん話し合った結果、私たちは超小規模の公立小学校を選ぶことにしました。
今回は、その選択に至るまでの過程や、小規模校のどんなところが息子にとって良さそうだと感じたのか、
実際に調べたり考えたりしたことを、わが家の目線でまとめてみようと思います。
なかなか新しい環境に馴染めない子
HSC(ひといちばい敏感な子)である息子は、現在、少人数で穏やかなリズムのなかで過ごせるシュタイナー教育の保育園に通っています。
全園児合わせても20人ほどの小さな園ですが、息子が安心して通えるようになるまでには1年半以上の時間がかかりました。
今でも、週明けや気分の揺れによって、登園しぶりが起きる日があります。
家じゃないばしょで、お昼寝するのイヤだよ。
五感の過敏さに加え、日韓の二重言語環境、母子分離不安など、乗り越えるべき壁は多々ありました。
それでも、少しずつ成長するなかで、今では友だちと仲良く遊べるようになり、知らない子とも遊びを通じて関われるようになっています。
保育園が本人に合った環境であっても、馴染むまでには時間がかかるという事実。
それを身をもって感じたからこそ、来年迎える「小学校入学」は、息子にとって大きな通過点だと考えています。
もし大きな学校に入学することになれば、まず人数の多さに圧倒されてしまうのではないかという心配があります。
周囲の変化に敏感な息子は、不安を感じると他人の動きひとつひとつが気になってしまい、落ち着かなくなるタイプ。
担任の先生やクラスメイトが、息子のペースに合わせて待ってくれる環境があるのかどうか、それがとても気がかりです。
目標は「毎日しっかり通うこと」
私たち家族は、韓国・ソウル近郊で暮らしています。
子育て世代が多く、学校もたくさんあります。
学区の小学校に自動的に進学するのが一般的ですが、我が家はHSCの息子にとってどんな学校が最適かを優先し、慎重に選ぶことにしました。
学区内にある中規模の公立小学校は、1学年2クラス、クラスあたり20人程度。
昔に比べれば十分少人数ではありますし、勉強だけでなく運動や遊びにも力を入れている、魅力的な学校です。
実際に、「できればここに通わせたい」と思えるほど印象は良好でした。
でも、息子にとっては、その人数でも負担になる可能性が高いと感じました。
そんななかで、徒歩圏内にある、ひっそりと建つ超小規模な公立小学校を偶然見つけたのです。
なんと、1学年1クラス、1クラス10人前後。
地域の再開発前からある、歴史のある学校で、今では周囲のマンモス校の影に隠れてひっそりと存在しています。
ちなみに、韓国での「小規模校」の定義は、全校で11学級以下の学校だそうです。
この学校はまさにそれに該当し、規模・距離・雰囲気のすべてが我が家の希望にぴったりでした。
それまでは、「息子にはシュタイナー系列の私立校しか合わないかもしれない」と思っていましたが、
現実的には引っ越しが必要なほど遠く、学費も非常に高額。
悩み続けていたなかで、近所のこの公立小規模校を見つけられたことは、本当に幸運だったと感じています。
正直、もしこの学校がもっと遠かったとしても、通わせたいと思ったかもしれません。
それくらい、息子にとって「安心できる環境」であることが大切です。
毎日送り迎えをする生活のなかで、何かあってもすぐに駆けつけられる距離にある学校というのは、本当にありがたい存在。
韓国では、低学年の間は集団登下校がないため、保護者が送迎することが一般的で、そういった点でもとても助かります。
これから始まる小学校生活。
まず目指すのは、「毎日しっかり通うこと」。
そこから少しずつ、安心できる日々を積み重ねていければいいなと思っています。
小規模学校のメリット・デメリット
我が家は、小規模な公立校が候補に挙げましたが、とはいえ、どんな学校にもメリットとデメリットはあります。
実際に通ってみなければ、先生や友だちとの相性は分からないものです。
大中規模校と小規模校では、学校の雰囲気や活動内容にも大きな違いがあるので、特性を知ったうえで、わが子の性格や気質に合うかどうかを見極めることが大切だと感じています。
小規模学校のメリット
- 先生の目が行き届きやすく、きめ細やかな指導が受けられる
- 落ち着いた環境で、学習にも集中しやすい
- 生徒同士のつながりが深く、全体にまとまりがある
- 子どもの存在感が大きく、自信や自己肯定感につながりやすい
小規模校ならではの、家庭的な温かさがあります。
学年を超えて交流する機会が多く、先生や保護者との距離も近く感じられるのが特長です。
今通っている小規模のシュタイナー保育園でもそうですが、何か困ったことが起きたとき、先生・保護者・子どもが一緒になって考え、解決していく姿勢が自然に育まれている気がします。
こうした環境では、親子で課題解決に向き合う力や、集団の中で自分の役割を見つけていく力も、ゆっくりと育っていくのではないかと思います。
もちろん、小規模ならではの関わりの濃さが負担になる場合もあるかもしれません。
保護者の出番が多いので、人付き合いが苦手な人にはプレッシャーになることも。
私自身もどちらかといえば得意ではないのですが……
ここはもう「自分の課題」として、前向きに向き合っていくつもりです(というか、やるしかない・笑)
小規模学校のデメリット
- 生徒数の減少により、統廃合の対象になる可能性がある
- 交友関係が限定的で、多様な考え方に触れづらいことがある
- 人間関係の選択肢が少なく、トラブル時の逃げ場がない
- 保護者同士の距離が近いため、人間関係に気を遣う場面が多い
- 学校行事などのスケールが小さく、盛り上がりに欠けることもある
私自身が一番気になっているのは、やはり「統廃合の可能性」です。
保育園でも、先生の確保が難しくて廃園になるかもしれない、という経験があったため、少人数特有のリスクは少し気がかりです。
ただ、公立校の場合は仮にそうした動きがあったとしても、決定・実行までには時間がかかるはず。
いまの時点では心配しすぎず、もしそのときが来たら、そのときにまた向き合えばいいと考えるようにしています。
また、小さな学校では年度ごとの受け入れ人数が限られていることもあります。
特に学区外からの入学を検討している場合は、早めに学校に問い合わせるのがベストです。
学校の人気や空き状況は年によって変わることも多いので、気になることがあれば、まずは電話で聞いてみるのがおすすめです。
電話での対応の雰囲気からも、その学校の空気感が少し見えるかもしれません。
学校情報はママ友・パパ友からも
それでは、小学校の情報収集はどうすればよいのでしょうか?
情報の質と量によって、選択肢の広がりが変わるのは確かです。
なるべく早めに、できるだけ多くの候補をリストアップしておくことをおすすめします。
私の場合は、まずインターネットで「どんな小学校があるのか」をリサーチするところから始めました。
学校の規模や特色、少人数制の学校がどこにあるのか、通学可能な範囲で数校をピックアップしていきました。
とはいえ、韓国の学校の雰囲気は私には未知の世界。
韓国語もあまり得意ではないので、情報を集めるのは正直ひと苦労でした。
調べた内容は夫に共有して、夫が改めて詳細を調べたり、直接学校に問い合わせたりしてくれたので、学校探しは完全に夫婦の協力作業でした。
でも、やはりいちばん頼りになるのは「リアルな声」。
保育園には、先生として学校で働いているママ・パパが多いので、そうした方々から学校の様子を聞かせてもらう機会がとてもありがたかったです。
つい先日は、実際に小規模小学校にお子さんを通わせている家庭があると聞き、お迎えに来ていたパパさんに思い切って話しかけてみました。
普段は無口そうな方で、挨拶程度の関係でしたが、いざ話してみるととても丁寧に、近隣のおすすめ学校や入学までの準備について詳しく教えてくださって、とても助かりました。
良い情報は、思わぬところにあるものです。
少し行動範囲を広げて、日常の中で出会う人との会話からも、子どもに合いそうな学校のヒントが見つかるかもしれません。
さいごに
たとえ子どもの性格や気質に合わせて選んだ学校でも、そのときの担任の先生やクラスメイトとの相性によって、学校生活の心地よさは大きく変わるものです。
先のことは誰にも分かりませんが、少なくとも今の息子にとっては、クラスの人数が少なく、人との関わりが自然に生まれやすい小規模校の方が、安心して自分らしさを出しやすいのではと感じています。
息子は、大勢の前で自分の意見を堂々と話せるようなタイプではありません。
だからこそ、日々の中で少しずつ関係が深まり、自然にやり取りが生まれていく小さな学校のほうが、息子にとって居心地の良い場所になるのではという思いで、我が家では小規模校を第一候補に決めました。
もちろん、人見知りの子どもを持つママ友の中には、あえて大規模校を選び、「たくさんの友だちと関わって成長してほしい」という考えを持つ方もいます。
その選択も素晴らしいと思いますし、家庭ごとに価値観や考え方が違うのは自然なことだと思います。
私のように、登園しぶりや登園拒否を経験した子どもを持つ親にとって、小学校入学はとても大きな関心ごとです。
学区外にも、個性ある学校はたくさんあります。
どんな学校なら、わが子が安心して、のびのびと通えるのか――
ゆっくり考えながら、子どもに合った環境を見つけてあげられるといいですね。