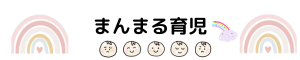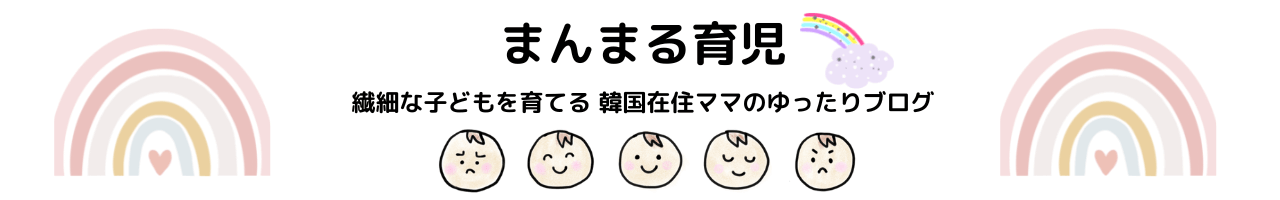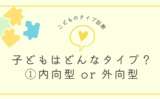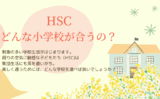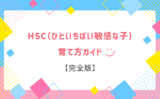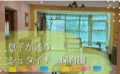「なんでこの子、こんなに育てにくいの…?」
そんな風に感じて、ひとり悩んだことはありませんか?
わが家の息子はHSC(ひといちばい敏感な子)。
一見おとなしくて「扱いやすい子」に見えるのに、突然感情が爆発したり、人との関わりが苦手だったり…。
育てる側としては「何に困っているのか」が見えづらく、ついイライラしてしまうこともありました。
でも、気質の違いを知ることで、「育てにくい」の正体が少しずつ見えてきたのです。
この記事では、HSCの子どもの気質をタイプ別(扱いやすい/扱いにくい/順応が遅い)に整理しながら、
接し方のヒントや実際の育児で役立った工夫を紹介していきます。
HSCの子の「気質」を理解する前に
HSC(ひといちばい敏感な子)の育児は、他の子と比べて「なぜこんなに疲れるの?」「どう接すればいいの?」という戸惑いが多くなりがちです。
そんな時、感情や行動の“理由”を探す手がかりになるのが「気質」の理解です。
気質とは、生まれつき備わっている刺激への反応のしかたや、行動の傾向のこと。
性格とは違い、先天的なものでありながら、成長にともなって安定していく特性です。
その気質を理解するために世界的に知られているのが、アメリカの発達心理学者・アレクサンダー・トマス博士らによる研究。
彼らは子どもの行動傾向を9つの視点から分類し、そこから4つの性格タイプに整理できることを示しました。
アレクサンダー・トマス博士による9つの気質特性
以下は、そのトマス博士らが提唱した「子どもの気質を理解する9つの視点」です。
HSCに限らず、すべての子どもに当てはまる基本的な枠組みでもあります。
- 活動性:よく動く or 落ち着いている
- 規則性:生活リズムが一定 or バラバラ
- 新奇性への反応(チャレンジ力):新しいことに積極的 or 警戒心が強い
- 順応性:変化にすぐ慣れる or 慣れるのに時間がかかる
- 反応の強さ:感情表現が激しい or 穏やか
- 感覚の敏感さ:音・光・肌ざわりなどに敏感 or 鈍感
- 気分の質:ポジティブ傾向 or ネガティブ傾向
- 行動の可変性:切り替えが早い or 一つにこだわる
- 集中力:長時間集中できる or 気が散りやすい
これらの特性は、子どもを観察することで「強い・普通・弱い」と大まかに把握できます。
組み合わせによって、のちに紹介する「4つの気質タイプ」へと分類されていきます。
息子の気質を客観的に見てみたら…
この9つの特性に照らし合わせて、わが子を観察してみると、意外な発見がありました。
私の息子の場合は──
こうして見ると、“落ち着きがない”“こだわりが強い”“環境の変化に弱い”といった行動にも、ちゃんと理由があったのだと気づけました。
「育てにくい子」と感じていたのは、実は「その子の気質を理解していなかっただけ」だったのかもしれません。
このように、まず子どもの気質を客観的にとらえることは、親のストレスを減らし、接し方のヒントにもつながります。 次のセクションでは、この9つの特性をもとに整理された4つの気質タイプをご紹介します。
子どもの気質タイプは4つに分けられる
トマス博士の研究では、先ほど紹介した9つの特性の組み合わせから、子どもは大きく次の4タイプに分類できるとされています。
それぞれのタイプには特有の特徴があり、親が感じる「育てやすさ」「育てにくさ」にも関係しています。
扱いやすい子(いわゆる「手のかからない子」)
このタイプの子は、気分が安定していて生活リズムも整っており、新しい人や環境にも比較的スムーズに適応できます。 園や学校にも比較的ストレスなく通え、集団生活にも自然に馴染める傾向があります。
育児のストレスが少ないため、「親が育てやすい」と感じることが多いタイプです。
順応が遅い子(slow to warm up)
慎重で、新しい環境や人に慣れるのに時間がかかるタイプ。 初対面では引っ込み思案になりやすく、慣れるまでに時間が必要です。
生活リズムや感情は比較的安定しており、無理をさせなければ問題なく過ごせることが多いです。
育児のポイント:
急がせず、その子のペースを尊重すること。 少しずつ慣れる機会を積み重ねていくことが大切です。
扱いにくい子(いわゆる「手のかかる子」)
感情の起伏が激しく、生活リズムが不規則、新しい刺激への反応も強め。
集団生活に慣れるのに苦労することもあり、親の忍耐力が求められます。
育児のポイント:
感情的なやりとりを避け、一貫した対応を心がけること。
「感情を受け止めてもらえる」という安心感が、徐々に行動の安定につながっていきます。
平均的な子
上記3タイプのどれにも極端には当てはまらない中間的なタイプ。 さまざまな特性をバランスよく持っており、状況によって扱いやすくも扱いにくくもなる傾向があります。
親としては一見「特に問題がない」ように感じますが、気づきにくい困りごとが潜んでいるケースもあります。
次のセクションでは、こうしたタイプごとの特性をふまえて、HSCの子どもに合った接し方・育て方について私の実体験を交えながらご紹介していきます。
HSCの子どもに合った育て方のヒント
こうしたタイプ別の気質を理解したうえで、HSCの子どもに合った育て方を考えることが、毎日の育児をラクにしてくれる大きなヒントになります。
ここでは、私自身の育児経験から見えてきた、気質に寄り添った接し方の工夫を紹介します。
基本的なことですが、やはりHSCには細やかな配慮が必要だと感じます。
安心できるルーティンを作る
敏感な子ほど、予測できない変化にストレスを感じやすくなります。
そのため、毎日の生活に「決まった時間」「決まった場所」「決まった流れ」を取り入れることで、心が安定しやすくなります。
わが家では、毎日同じ時間に同じ公園へ行くという小さなルーティンが、息子にとって大きな安心材料に。
決まった時間に同じことを繰り返すという、生活リズムをしっかり整えることを心掛けました。
否定せず“受け止める言葉かけ”を
「そんなことで泣かないの」「どうして怒るの?」と反射的に否定してしまいたくなる場面も多いですが、HSCの子には逆効果。
「びっくりしたんだね」「悲しかったね」と、まずは気持ちをそのまま受け止める言葉を返すことで、子どもは安心しやすくなります。
気持ちを言葉にする練習を少しずつ
HSCの子は感情が強く出る一方で、それをどう表現していいのか分からずパニックになることも。
日頃から「どんな気持ち?」「今、怒ってる?」などと声をかけることで、自分の気持ちを言語化する力が少しずつ育っていきます。
園や学校との連携を大切に
家庭内だけで抱え込まず、保育園や学校の先生と子どもの特性を共有することもとても大切です。
「急な変更が苦手です」「初めてのことに緊張しやすいです」など、具体的に伝えることで、子どもに合った配慮がしやすくなります。
HSCで“扱いにくい子”だった息子の実体験
私の息子も、「扱いにくい子」に分類されるタイプです。
とにかく癇癪が多く、感情が激しく、場所見知りもひどい。
外に連れ出すだけでひと苦労、集団の中では泣いて固まる──そんな日々が何年も続きました。
よく耳にしたアドバイスは、 「もっと外に連れ出して慣れさせた方がいいよ」 「人との関わりが足りないのかもね」など。
もちろん善意のアドバイスだと分かってはいるのですが、HSCの子にとっては“刺激そのもの”が強すぎる場合も多く、 一概に「慣れさせればいい」という話ではないのだと、私は身をもって知ることになりました。
私が意識していたのは、 「環境を変える」のではなく「安心できる環境に繰り返し身を置くこと」。
たとえば、毎日同じ時間に同じ公園に行く。
そこで誰とも話さなくても、遊ばなくてもいい。ただ“いる”だけでOK。
するとある日、息子の方が「ちょっと遊びたい」とつぶやいたのです。
その日を境に、ほんの少しずつ世界が広がっていきました。
子どもが一歩を踏み出すには、「安心」という土台が必要なんだと実感した瞬間でした。

成長とともに変わったこと(現在の様子)
そして今、小学1年生になった息子は──
怒りっぽさや癇癪も、ゼロではないけれどずいぶん落ち着いてきました。
何より、まわりの様子を見ながら行動できるようになってきたことに、日々成長を感じています。
もちろん、敏感な気質は今でも残っていて、新しい環境に戸惑ったり、緊張したりする場面もあります。
でも、あの「毎日泣いてばかりだった日々」と比べると、 いまは確かに、前を向いて歩いている姿がそこにあります。
さいごに
HSCの子どもを育てていると、「普通」に合わせることの難しさを痛感します。
保育園や学校での集団生活、周囲のアドバイス、年齢相応の期待──。
でも、HSCの子にはその子なりのペースや得意・不得意があり、それに合った関わり方が必要です。
今回は、気質の違いによって育てやすさが変わること、そして接し方の工夫によって“その子らしさ”を尊重した育児ができることをお伝えしてきました。
一番大切なのは、親が「困っている行動」の背景を知ること。
ただ叱るのではなく、「なぜ今こうしたのか?」を理解しようとする視点が、親子の関係を少しずつ変えていくと感じます。
どんな子にも、安心できる環境と、見守ってくれる大人の存在が必要です。
すぐに変わらなくても大丈夫。 今日できなかったことが、明日少しできるようになる。
HSCの子どもと関わる日々には、難しさと同時に、深い学びや成長の瞬間もたくさん詰まっています。
そのひとつひとつを積み重ねながら、親も子も一緒に育っていけたらいいですね。