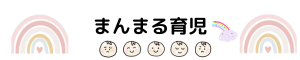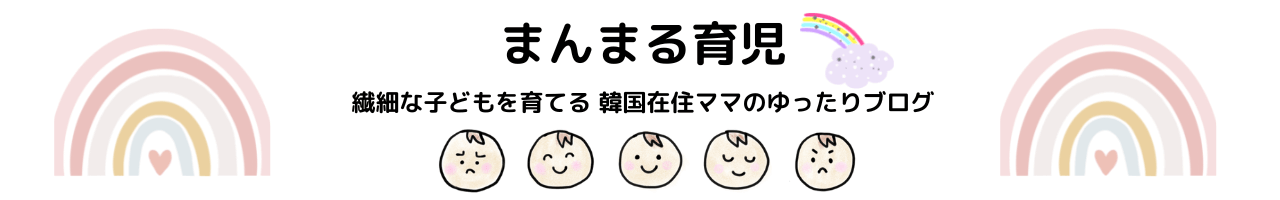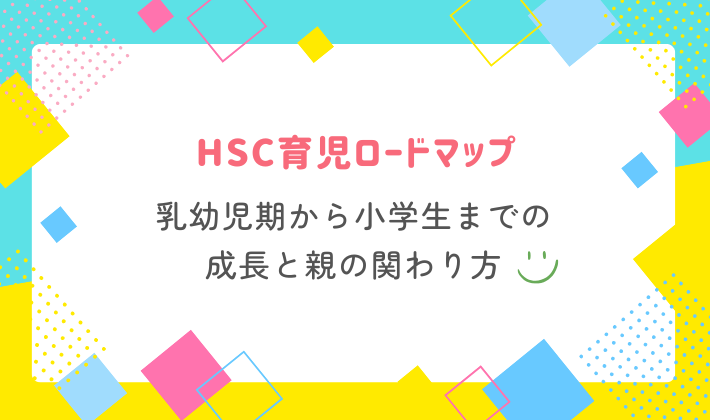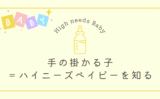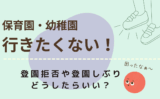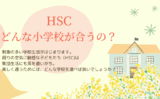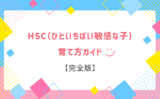「毎日泣いてばかり、寝ない、すぐびっくりする——」
赤ちゃんのころから“ちょっと育てにくいかも?”と感じたことはありませんか?
もしかしたら、それはHSC(ひといちばい敏感な子)の気質かもしれません。
とはいえ、HSC育児って“特別な子のための難しい育児”ではなくて、
ただ「感じ方が少し深い子」に合わせたちょっと優しい工夫の積み重ねなんです。
うちの息子も、まさに敏感っ子。
新しい環境では毎回リセットボタンが押され、登園しぶり・母子登校・小学校選び……と、山あり谷ありの連続でした(正直、親の方が泣きたい日もありましたが笑)。
この記事では、そんな我が家の体験をもとに、
乳幼児期から小学校低学年までの“HSC育児ロードマップ”をまとめました。
「今のうちの子の段階で、どんなサポートを意識すればいいか」
きっと見つかると思います。
🍼 第1章:乳幼児期 ― 「泣く・寝ない・離れない」時期
赤ちゃん期からすでに「育てにくさ」を感じていた方も多いと思います。
実はそれ、“性格”ではなく“気質”のサインかもしれません。
私も当時は「どうしてこんなに泣くの?」と悩み続けましたが、
「ハイニーズベイビー」という言葉に出会ってから、視点が変わりました。
泣く・寝ない・離れない。そんな毎日の中でも、
子どもが“安心”を感じられる瞬間を見つけることが、HSC育児の第一歩でした。
👶 HSC(敏感っ子)乳児のあるある
HSCの赤ちゃんは「刺激フィルター」が薄め。
大人が“気にならない音や光”も、全身でキャッチしてしまいます。
だから泣くのは、“困ってる”のではなく、“処理が追いつかない”だけなんです。
☁️ 「抱っこばかりで進まない日」も、大事な時間
当時の私は「何もできてない…」とよく落ち込んでいました。
でも今思えば、“抱っこしかできない日”こそが、
この子の「安心のストック」を作っていたんだと思います。
敏感な赤ちゃんほど、「抱かれて安心した経験」=「自信の種」。
それが後の“人を信じる力”につながっていくんです。
(抱っこは愛情筋トレ💪)
🌙 「寝ない・泣く」夜に試してよかったこと
HSC育児に必要なのは、「完璧」じゃなく「諦め上手」。
泣く日も成長のうち——そんな気持ちで、自分にも優しくしてOKです。
💡 この時期のキーワード:「安心感の貯金」
いっぱい泣いて、いっぱい抱かれて——
それがこの子の“心の基礎体力”になります。
🧸 第2章:園生活期 ― 登園しぶりと母子分離
保育園・幼稚園が始まると、次の壁が「登園しぶり」です。
朝の玄関で泣きじゃくる子どもを前に、「どうしたらいいの?」と立ち尽くす朝も。
HSCの子は、環境変化や人の表情にとても敏感です。
だからこそ「泣かせないようにする」よりも、
「泣いても大丈夫」と伝える関わりが必要になります。
母子分離の第一歩は、子どもよりも“親の安心”から始まるのかもしれません。
🧸 登園しぶりの正体
HSCの子は、新しい環境・音・人に敏感。
朝の準備の段階で、もう頭の中がフル稼働して疲れてしまうんです。
わが家でも、4歳のとき“保育園逃亡事件”がありました。
園までは行くのに、どうしても入れないという息子。
仕方ないので、目の前の公園まで先生に迎えに来てもらい、
息子は全力で逃げ回るという……(苦笑)
先生には申し訳ないし改善の気配は全くないしで当時は本気で悩みました。
🌈 登園しぶりをやわらげる3つの工夫
1️⃣ 朝の流れを固定化する
2️⃣ 別れるときはキッパリと
3️⃣ 小さな成功を積み重ねて褒める
そして、“どうしても無理な日”は休ませる勇気も。
休むことも登園練習の一部です。
💬 「泣いてもいい」を合言葉に
途中から私は“泣かせない”より“泣いても大丈夫”を意識しました。
「泣いても行けたらすごいね」と声をかける。
泣いても行けた経験=成功体験。
泣きながらも頑張った姿こそ、HSCの子の“自信の種”になります。
💡 この時期のキーワード:「安心して離れる」
母子分離の目的は「離れること」ではなく、「信頼を積み重ねること」。
「ママは必ず戻ってくる」と感じられることが、HSCの子の最大の支えになります。
🏫 第3章:小学校期 ― 集団の中での揺れと成長
小学校に入ると、新しい刺激との付き合い方がテーマになります。
クラスのペース・人間関係・先生との相性…HSCの子にはどれも大きな課題です。
「合う環境」を見つけることは、HSC育児における最大のサポートです。
完璧な学校はないけれど、「安心できる場所」は必ずあります。
🌼 「行きたくない」は、成長の途中にある“通過点”
入学式の朝、泣かずに席に座る息子の姿を見て、胸が熱くなりました。
たったそれだけのことでも、あの頃の私には大きな一歩。
でも、入学直後から登校しぶりはやっぱり再発。
最初の2か月は付き添い登校が続きました。
それでも、ある朝ふと「今日はひとりで行ってみる」と言って校門をくぐった姿は、忘れられません。
HSC育児では、“一歩前進”はいつも静かにやってくるものです。
泣かなくなる日より、「行けた日」を見つけてあげるほうが大事なんだと実感しました。
🧒 クラスの中で「自分を出す」練習
HSCの子は、場の空気を読むのが上手です。
でもその分、「自分の意見を言う」ことにブレーキがかかってしまうこともあります。
海外の学校では自己主張の強い子が多く、息子も「言いたいのに言えない」経験を何度もしてきました。
家庭ではできるだけ「今日はどんなことが印象に残った?」と聞きながら、
“自分の感じたことを言葉にする練習”を続けています。
小さな話題でも、「感じていい」「話していい」が伝わると、
子どもは少しずつ“自分を表現できる安心”を身につけていきます。
🌈 「登校しぶりの再発」は後退ではなく、心の調整期間
1年生では2か月、2年生では3か月かけて、付き添い登校から一人登校へ。
それでも長期休みのあとには、また“行きたくない”が顔を出します。
でも、それは後退ではなく、成長に伴う心の調整期間。
自分で「不安だ」と感じ取れるようになった証拠です。
今では、「行きたくない!って言いながら行くけど〜」
と笑いながら出発するようになりました。
不安で行きたくない気持ちも本心。
それでも自分のやるべきことを理解して前に進むようになったのは、
まぎれもなく“心の成長”です。
HSCの子は、泣きながらも、ため息をつきながらも、ちゃんと前に進んでいます。
親にできるのは、その小さな一歩を「ちゃんと見てるよ」と伝えてあげること。
💡 この時期のキーワード:「歩幅をそろえる」
学校生活は、マラソンのようなもの。
ペースを乱さず、親子で“歩幅をそろえる”ことが何より大切です。
泣いても止まっても、今日はここまで行けたなら、それでOK。
一緒に立ち止まる時間も、ちゃんと成長の一部。
焦らず、比べず、見守りながら。
それが、HSCの子にとっていちばん安心できる“伴走”の形です。
🪞 第4章:8〜10歳ごろ ― 自立と自己肯定感の芽生え
小学校中学年になると、子どもの世界がぐっと広がります。
まだ“甘えたい気持ち”と“自分でやりたい気持ち”が入り混じるこの時期は、
いわば「心の思春期=プレ思春期」の始まり。
HSCの子は特に、他人の気持ちに敏感なぶん、
「どう感じるか」「どう表現するか」で悩むことが増えていきます。
でもそれは、“心の自立”が始まっている証拠です。
🌼 「どう感じた?」を一緒に言葉にする
この頃の子どもは、他人の感情はよく読めても、
自分の気持ちはまだ整理が難しいものです。
「○○ちゃんが怒ってた」
「先生がそう言ってた」
こんなふうに“他人の気持ち”を代弁することが増えてきたら、
「じゃあ、あなたはどう思った?」と優しく聞いてみましょう。
うまく答えられなくてもOK。
「わからない」「モヤモヤする」も立派な答えです。
HSCの子にとって、「気持ちを持っていい」と受け止めてもらうことが、
自己肯定感のスタート地点になります。
💬 「できた」より「感じた」を喜ぶ
テストや運動会など、成果が見える機会が増えるこの時期。
でも、HSCの子は“結果”よりも“心の動き”で成長します。
「今日は緊張したけど頑張ったね」
「昨日より楽しそうだったね」
そんな声かけを意識するだけで、
「できなくても大丈夫」「頑張った自分も好き」と思えるようになります。
🪞 「失敗=ダメ」ではなく「次に活かせる」に変換
HSCの子は真面目で完璧主義な一面もあります。
たとえば聞き取りテストで1問だけ間違えて落ち込む、
友だちに注意されただけで自分を責めてしまう。
そんなときは、「間違えた=悪いこと」ではなく、
「次に気づけた=すごいこと」と言葉を置き換えてあげましょう。
「失敗しても、あなたの価値は変わらない」
この一言が、HSCの心に“自己肯定の根”を残します。
☀️ 親の姿から「完璧じゃなくていい」を学ぶ
HSCの子は、驚くほど親をよく見ています。
ママやパパが落ち込んでいたら、「どうしたの?」と先に気づくほどに。
だからこそ、親自身が「完璧じゃなくても大丈夫」と見せてあげることが大切です。
「私も小さいときは学校行きたくないときもあったよ」
「うまくいかなかったけど、ま、いっか!」
そんな日常の言葉から、
「同じことで悩むこと」や「立ち直れる」姿を学んでいきます。
🌻 親ができる3つのサポート
1️⃣ 感情ワードを使う
「悲しい」「悔しい」「うれしい」などの感情を、日常会話でよく使うことで、
子どもが自分の気持ちを言葉にしやすくなります。
2️⃣ 味方であることを言葉で伝える
「何があっても味方だよ」
「いつでも話を聞くからね」
言葉にするたび、子どもの中に“安心の貯金”がたまっていきます。
3️⃣ “優しさのルール”を家庭で決める
「疲れた日は休んでOK」「できたら一緒に喜ぶ」など、
目に見えない安心のルールを共有しておくと、
HSCの子は家庭を“安全基地”として感じられるようになります。
🌈 さいごに ― 自立は「信じて待つ」ことから始まる
HSCの子は、感じる力が深い分、成長のテンポも独特です。
親が心配して先回りしたくなることも多いけれど、
“信じて待つ”ことも立派なサポートです。
私もつい、「大丈夫?」「忘れ物ない?」と何度も声をかけてしまいます。
最近は息子に「小言おおすぎ~」と言われるようになりました。
……それもまた、立派な成長のサイン。
ゆっくりでも、自分の言葉で世界と関わる勇気を育てていくこの時期を、
どうか焦らず見守ってあげてください。
その一歩は、小さくても、確かな成長の証です。