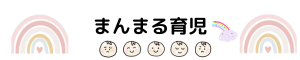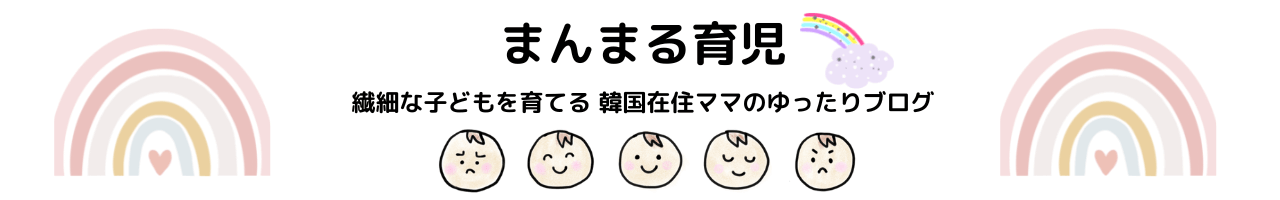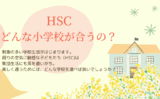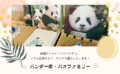少人数の保育園や学校を選んできたわが家。
落ち着いた環境でのびのび過ごしてほしい──そんな思いから選んだ小規模保育園は、卒園を待たずして閉園の危機に。なんとか卒園できたものの、今度は入学したばかりの公立小学校で「統廃合」の話が出てきました。
「え、また?」
正直、頭を抱えました。
今の時代、少人数制は合っていないのかもしれません。
それでも我が家が“小規模”にこだわってきた理由があります。
今回は、韓国在住の母として、小規模校に通う息子と過ごした揺れる1年を、リアルに振り返ります。
当時の状況:またもや「閉鎖」「統合」の文字
息子はHSC(Highly Sensitive Child/ひといちばい敏感な子)気質が強め。
静かで落ち着いた環境のほうが合っていると感じ、保育園も小学校も少人数を重視して選びました。
そんな我が家にとって、小規模校の閉鎖や統廃合の話は本当にダメージが大きいもの。
保育園はギリギリで卒園できたものの、小学校では入学してしばらくすると統廃合の検討が始まったのです。
しかも、そのスピード感が想像以上。
「うわさレベルかな?」と思っていたら、翌日にはPTAから連絡。
教育庁からの封書、説明会、保護者投票…と、次々に予定が入りました。
極めつけは、まだ何も決まっていないはずなのに校舎の修繕工事が始まっていたこと。
「これって、もう決まっているってこと…?」
正直、そう感じてしまうほどの急展開でした。さすが韓国(苦笑)。
親として感じた葛藤と選択
「今の学校を守ってあげたい」
でも、現実には厳しい条件もありました。
統合に反対すると補助金がカットされたり、複式学級(1・2年生が同じ教室になる)になる可能性が出たり。
それでも、保護者の投票は見事に賛否が真っ二つに分かれました。
特に、最初からこの学校を希望して入学した家庭にとっては、「この環境を変えたくない」という思いが強くあり、わが家も息子の「ここが好き」という気持ちを大切にしようと決めました。
息子の様子と、小規模校の“豊かさ”
1年生の息子は、学年を超えた交流を楽しみに学校に通っていました。
放課後のスポーツ活動では6年生と一緒に練習し、最初は手加減されていたのが、最近は本気で勝負してもらえるように(笑)。
こうした異学年とのつながりや、地域の方との体験授業など、人数が少ないからこそ実現できる学びがあります。
また、少人数制だから先生の目も届きやすく、ほぼマンツーマンに近い丁寧な対応をしてもらえるのも大きな安心でした。
毎年続く「存続」の投票、でも希望もある
昨年は、なんとか統合案が見送られました。
そして2025年からは、毎年「統廃合に賛成するか否か」の投票を続けていくという方針に。
それでも、学校とPTAが力を合わせた結果、今年は予想以上の新入生が入ってきました。
このまましばらくは、学校としての存続が見込めそうです。
実際、他の地域の小規模校の中には、独自の教育スタイルや特色あるカリキュラムで人気を集め、統廃合対象になっても存続しているケースもあるようです。
今振り返って思うこと:小さな学校が持つ“価値”
「人数が少ないから不便」「非効率」──確かにそう感じる場面もあります。
運動会などは毎年、工夫と苦労の連続です。
でも、その不便さを超える価値が、小規模校にはあると信じています。
学区外からも希望して通う子がいる「特認校」であるこの学校には、のびのびとした空気感と、一人ひとりを大切にする姿勢があります。
学校と保護者が力を合わせて「どうしたら今の環境を維持できるか」を考え続けてきました。
それでも、時代の流れや教育制度の変化の中で、小規模校の存続がますます難しくなっている現実も、肌で感じています。
さいごに:これからも、子どもの気持ちを一番に
わが家は、小さな園と学校の温かい雰囲気に惹かれて、今の環境を選びました。
その選択は、間違いなく「正解」だったと思っています。
子どもたちはのびのび育ち、先生たちも親身で、心のこもった教育が行われている。
この学校に出会えて本当に良かった。
これからまた、進路について考える場面が出てくるかもしれません。
でもそのときは、子どもの気持ちを一番に、柔軟に向き合っていきたいと思います。
小規模校には不便もリスクもあります。
それでも「ここでなら安心して通える」と思える場所があることは、HSCの子にとっても、親にとっても大きな支えになるのではないでしょうか。