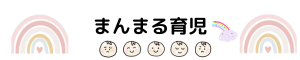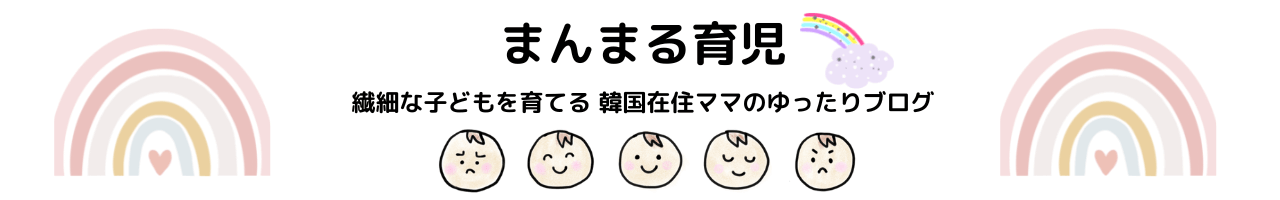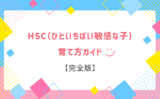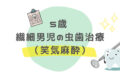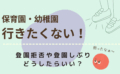今年、年長になった息子は、年少の途中(3歳半)から韓国にあるシュタイナー保育園に通っています。
とはいえ、我が家の場合、最初から「シュタイナー教育で育てたい!」という明確な教育方針があったわけではありません。
たまたま小規模で穏やかな雰囲気の園が近くにあると知り、HSCの息子に合いそうだと感じて選んだのがきっかけです。
シュタイナー教育については、入園前はまったく知識のない状態でした。
それでも入園から2年が経った今、実際に通わせてみて感じたことや、一般的な園との違いについて、少しずつ見えてきたものがあります。
この記事では、そんなシュタイナー園での保育の様子や、HSCの息子との相性、親としての気づきなどを、リアルな視点でお話ししていきたいと思います。
シュタイナー保育園に入園した経緯
現在私たちが暮らしている韓国では、赤ちゃんの頃から保育園に通わせる家庭が多く、あちこちに園が点在しています。
専業主婦であっても、保育園に子どもを預けることはごく一般的な文化です。
私の息子は、ひといちばい敏感な子で、特に初対面の人や新しい環境に不安を感じやすいタイプ。
そのため、「保育園に通わせるなら年少から」と決めており、最初に選んだのは近所の私立保育園でした。
その園は韓国らしく、週に数日は英語や体操など、外部の専門講師によるカリキュラムが組まれていて、
お勉強も遊びもイベントも充実しており、子どもが楽しく通えるようにさまざまな工夫がされている園でした。
ただ、その刺激の多さや活動の密度が、息子には負担が大きすぎたのだと思います。
HSCの特性として、「慣れるまでに時間がかかる」「刺激に敏感で疲れやすい」という傾向があり、結果として、登園しぶり・登園拒否が続いてしまいました。
先生方には息子の気質をうまく理解してもらえなさそうだったこともあり、わずか3ヶ月で退園を決意しました。
その後、転園先を探していたとき、偶然友人から「小さい保育園があるよ」と教えてもらったのが、今のシュタイナー保育園との出会いでした。
見学に行ってみると、一般的な保育園とは雰囲気がまったく違い、「ここなら、息子が安心して過ごせるかもしれない」
そう直感的に感じ、3歳半のタイミングで入園を決めました。
見学に行って驚いたこと


保育園の見学に行く前に、少しだけシュタイナー教育について調べてみました。
名前だけは知っていたものの、教育内容は全く知らず、人気のモンテッソーリ教育との違いすら分からない状態でした。
調べていくうちに分かったのは、
シュタイナー教育は全く異なる価値観と方法で子どもと向き合う、かなり個性的な教育だということ。
一般的な保育園とも、まったく雰囲気が違うということがわかりました。
実際に見学に行って、まず驚いたのが園庭にある遊び道具でした。
使われていたのは、韓国の家庭でよく見かける、もう使わなくなったステンレスのコップやスプーン、フライパン、鍋など。
プラスチックのおもちゃは一切見当たらず、今でこそ見慣れたこの光景も、当時はかなりの衝撃でした。
「えっ、これで遊ぶの……!?」
園の中も、やはり一般的な保育園とはまったく違う雰囲気でした。
キャラクターもののおもちゃはなく、代わりにあるのは、木製の積み木、毛糸で編まれた人形、自然の素材(石、貝殻、木の実など)を使った“おもちゃ”。
お部屋の中はとても落ち着いた空気が流れていて、視覚的にも刺激が少なく、優しい空間でした。
そしてもう一つ印象に残っているのが、息子に出してくださった「おやつ」。
なんと、乾パンでした(笑)
「えっ、乾パン?!」と心の中で驚いたのをよく覚えています。
でも今では、息子は普通におやつとして乾パンを食べているので、慣れって不思議なものです。
個人的には、
「今どきの保育園とずいぶん違うけど、この雰囲気、すごく好き…!」
と、見学の時点で直感的に惹かれるものがありました。
“シンプルだけど豊か”な空間に、どこか懐かしさと安心感を覚えたのだと思います。
見学からすぐに面談、そして入園決定


やわらかで穏やかな園内
大きな声や怒る声が苦手な息子にとって、ゆっくり穏やかに話す先生たちの存在は、とても心地よかったようです。
シンプルで落ち着いた内装、優しい雰囲気の中で、
敏感な息子だけでなく、子どもたちや親にとっても、安心感のある空間がそこにはありました。
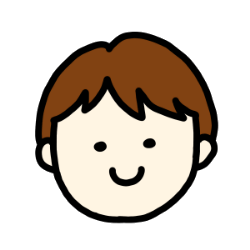
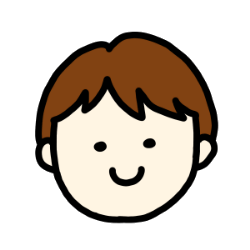
ここ、いいね。気に入ったよ。
そんな言葉が、息子の口から自然と出てきたのが、印象的でした。
丁寧な面談と、入園の決断
見学のあと、園長先生との面談が行われました。
およそ1時間にもわたる長い面談で、息子の状況をひとつひとつ丁寧に聞いてくださり、園としてどのように関わっていけるかをゆっくり説明してくださいました。
息子は慣れない場所だったため、1人で遊ぶことはせず、私のそばを離れませんでした。
その分、かなり疲れた様子もありましたが、焦らせず、責めず、やさしく寄り添ってくださったことがとてもありがたかったです。
実は最初、入園を断られていました
実はこの園、当初は「3歳児の人数が多い」という理由で、入園を一度断られていたんです。
シュタイナー保育園では縦割り保育を基本としていて、年齢の比率が偏らないよう調整しているため、特定の年齢層が集中すると受け入れが難しくなることがあるそうです。
それでも諦めきれなかった夫が、
「せめて見学だけでも…」
とお願いしたことから、今回の面談につながりました。
園の判断と、入園の決定
そして、園長先生が息子に興味を持ってくださり、その場で入園が決定。
今思えば、息子が外では比較的大人しいタイプだったことや、活発な子の多いクラスとのバランスを見て、柔軟に対応してくださったのかもしれません。
子ども一人ひとりの気質(個性)や、クラス全体のバランスを大切にする園は、本当に珍しいと思います。
その姿勢に、とても安心感を覚えました。
2年通ってみて感じた息子の成長
入園当初の息子の様子はというと……正直、うまくはいきませんでした(汗)
給食は野菜が多くてほとんど食べられず、
音や雰囲気に敏感すぎて昼寝もできず、
なかなか母子分離もできず……。
慣らし保育には、通常2週間のところ、なんと3ヶ月もかかりました。
しかも午前保育にもかかわらず、私はずっと教室のそばに付き添う日々。
登園しぶりと登園拒否を繰り返し、まさに親子で消耗する毎日でした。
先生方も、「こんなに時間がかかる子は初めて」とおっしゃっていて、
私自身も「本当に5人に1人がHSCなの?」と疑いたくなるほど、周囲に同じような子がいない孤独感を感じていました。
いくら穏やかなシュタイナー園とはいえ、“新しい環境”というだけで、息子にとっては大きなハードル。
登園するたびに、「今日はどこまで先生に頼っていいのか」「どこまで待ってもらえるのか」を気にしながら、送り出していました。
言葉の壁も、少しずつ
韓国で暮らしていても、家庭では日本語中心の生活だったため、韓国語はほぼゼロの状態からのスタートでした。
言葉を話すことに対する恐怖心もあり、最初は発語も控えめ。
でも、1年目の終わりには聞き取る力がぐんと伸びてきて、今では、必要なことや興味のあることについては、自分の言葉でしっかり伝えられるようになってきました。
やっと、園が「楽しい場所」に
最近になって、ようやく閉園時間まで過ごせるようになり、
本人も園生活を楽しめるようになってきた様子。
人に配慮すること、自分の意見を言うこと――
少しずつ身についてきて、今は友だちとも自然に関わりながら過ごしています。
ケンカもできるようになりました(笑)
これも大きな成長だと感じます。
勉強や知育の時間がないぶん、人との関わりにしっかり向き合う時間が多かったのも、息子にとって良かったのかもしれません。
おかげで、今では友だちがたくさんできました。
シュタイナー園でない他の場所でも、いつかは園生活に慣れていたのかもしれません。
でも、「我慢して慣れる」のではなく、”先生や仲間の存在のおかげで“自然と慣れていった”という感覚があるからこそ、
この園でよかったなと、心から思っています。

戸惑うことがあっても、素晴らしい園
「シュタイナー教育」という名前は有名なので、一度は耳にしたことがある方も多いかもしれません。
でも、実際に通わせるとなると「どうなんだろう?」と、悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
シュタイナー園は「共同運営」が基本のため、保護者も運営に深く関わり、協力する場面がとても多いです。
親の努力と参加が不可欠な保育環境なので、入園を検討するときには、それなりの覚悟が必要かもしれません。
とはいえ、私自身はこの園に入ってみて、
「まるで田舎のおばあちゃんの家で子どもを預かってもらっているような、あたたかさと安心感がある」
と感じました。
自然な雰囲気や、ゆっくりとした時間の流れのなかで子どもを育てたい人には、ぴったりの環境だと思います。
見学会や慣らし保育の期間を通して、
「これがシュタイナー教育なんだ!」という教育理論を超えた“感動体験”を味わえることもあるかもしれません。
通常の保育園とはまったく違う空気感を、肌で感じられるはずです。
先生方はいつも寄り添って見守ってくださり、
庭で子どもたちがのびのびとおやつを食べる、そんな微笑ましい日常がここにはあります。
子どもは全身で学び、遊び、そして親もまた、共に学び直すような園――
そういう場所は、実はとても貴重なのではないでしょうか。
私自身も、息子の影響でテレビを見なくなったり、情報との付き合い方を見直すようになりました。
同じ価値観を共有できる保護者の方々と接することで、必要以上に比べたり焦ったりしない育児ができるようになりました。
結果的に、私自身も心が落ち着き、心地よい日々を過ごせるようになったと感じています。
さいごに
HSCの子どもには、「強い刺激が苦手」という大きな特徴があります。
騒がしい場所や突然の大きな音、イベントごとの多さ、
元気で大きな声の園児たち――
それらが苦手な子どもにとっては、園生活自体が強いストレスになってしまうこともあります。
「子どもは元気に大きな声で!」ができない子には、その子に合った、穏やかな環境を探してあげることが大切です。
園を選ぶ際は、方針・雰囲気・先生の対応などを見学時にしっかり確認することをおすすめします。
小規模でなくても、きっとその子に合う場所は見つかるはずです。
私自身、息子がHSCだったおかげでシュタイナー教育という世界に出会うことができました。
そのなかで、「幼児期に子どもが本当に必要としていることって、なんだろう?」と考えるきっかけを、たくさん与えてもらいました。
オーガニックの給食、季節の果物、自然の中でのびのびと体を動かす時間、
そして、先生の優しい歌声に包まれて過ごす毎日。
そうした環境の中で、息子は心も体も健やかに成長しています。
正直に言えば、「HSCでよかった」と思えることは、そんなに多くはないかもしれません。
でも、もし息子が“育てやすい子”だったら、私はこんなに深く幼児教育について考えることはなかったと思います。
シュタイナー教育の話が中心になってしまいましたが、
HSCに合った、安心できる環境の中で育った子どもたちは、
きっとその先の小学校生活でも、じょうずに自分のペースを見つけていける。
私は、そう信じています。