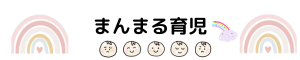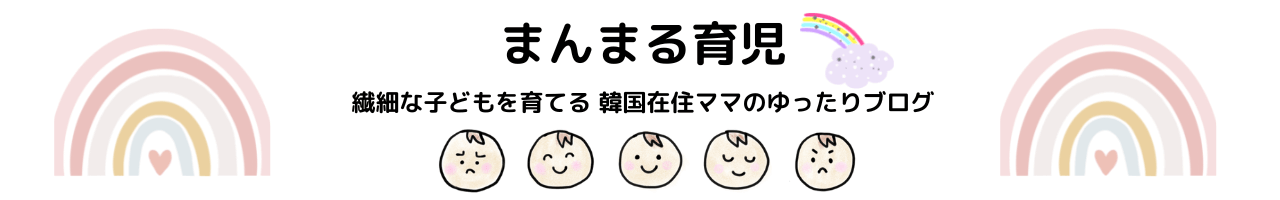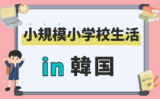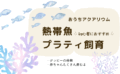こんにちは!
今回は、我が家の体験をもとに「小規模小学校って実際どうなの?」というテーマで書いてみます。
小学2年生の息子が通うのは、1学年10人ちょっとの小規模な公立小学校。
繊細な息子のために選んだ学校です。
入学前は「ちゃんと勉強できる?」「友だちはできるのかな?」と不安でしたが、
1年通ってみての実感は、「むしろ、この環境でよかった!」というものです。
この記事では、小規模校のメリットや誤解されやすい点などをリアルな視点でまとめました。
小規模小学校は教育レベルが低い?
よく言われるのが、「少人数すぎて授業がちゃんと成り立たないのでは?」という疑問。
でも、実際には、
大規模校の様子は詳しく分かりませんが、小規模校では「ちゃんと見てもらえている」と感じる場面が多くあります。
「教育レベルが低いのでは?」と心配されることもあるかもしれませんが、同じ公立校なので当然ですが、使用している教科書や学習進度はマンモス校と変わりません。
“競争”という観点では、確かに人数が少ない分、差が出にくいかもしれませんが、
発言の機会が多く、先生の目が行き届く環境なので、個別対応の手厚さを重視したいご家庭にはむしろおすすめの学習環境だと感じています。
熱心さは担任の先生による場合も
息子が2年生に進級して、マンモス校での指導経験が豊富な先生が担任になりました。
さすが、たくさんの子どもを見てきた先生だけあって、かなり熱心です(ちょっと熱心すぎるくらい笑)。
ちなみに、1年生のときの担任の先生は、とても優しい方でした。
初めての学校生活ということもあってか、宿題はゼロ、字の丁寧さやルールについてもあまり厳しくなかった。
そのときは正直、「小規模校だからゆるいのかな?」と思ったこともありました。
でも、2年生になって一気に“学習”らしい学びが始まった感じがします。
結局のところ、教育の雰囲気は学校の規模”ではなく、“担任の先生によって大きく左右される”ということを、1年間通って感じました。
友だちが少なくてかわいそう?
友だちが少ないとかわいそう・・。
小規模校に通わせる際、気になる方も多いのではないでしょうか。
うちの息子は、比較的誰とでも仲良くできるタイプですが、入学前は「少人数の中で合う子がいるかな?」という不安がありました。
でも実際には、
これは、小規模校ならではの特徴だと感じます。
小規模校では、他学年と一緒に授業や活動をする機会が多くあって、通常の授業はもちろん、放課後活動などでも他学年と関わる場面が多いため、年齢に関係なく仲良くなれる環境が整っています。
特に印象的だったのが、上級生が下級生を自然と気遣ってくれるところ。
面倒を見るというより、「当たり前に一緒にいる」感じで、まるで兄弟のように育っているように感じました。
1年生のころ、息子は学童に入っていなかったので、ひとりで待つ時間が多かったのですが、そんな時もお兄さんたちがそばにいて一緒に遊んでくれたので、安心して送り出すことができました。
私自身が「小規模校に通いたかった派」のため、どうしてもメリットばかり目に入ってしまいますが、あるクラスメイトのおばあちゃんは、「友だちが少ないのは寂しいわね」とおっしゃっていたこともあります。
でも個人的には、少ない=さみしいではなく、少人数だからこそ、一人ひとりと深く関われる関係が築けると感じています。
「たくさんの友だちがいる」よりも、“安心して過ごせる関係”があることは、子どもにとっては大きな意味があるのではないかと思います。
行事は少なめだけど濃さがある
たしかに、運動会や学芸会はこぢんまりとした印象かもしれません。
でもその分、
「派手さはないけど、濃い時間を過ごせる」というのが、素直な感想です。
学校主催の行事だけでなく、息子の通う小規模校では、PTA主催のイベントも意外と多くあります。
子どもたちは、そんな行事をいつも楽しみにしているようですし、私自身も保護者として手伝いに行く機会があるのが嬉しいポイント。
お母さんたちと交流できる場が多く、子どもの普段の様子を学校で直接見られるのは、安心につながっています。

保護者同士の関係性は?
小規模校というと、「保護者同士の関係が濃すぎるのでは?」と心配される方もいるかもしれません。
でも、うちの場合は適度な距離感が保たれていて、むしろ心地よい関係性が築けています。
必要なときには自然と助け合える雰囲気があり、過度な干渉や“付き合い疲れ”のようなものは感じません。
息子のクラスでは、ほとんどのご家庭が共働き。
そのため、保護者同士が顔を合わせるのは、お迎えのタイミングでたまに挨拶を交わす程度です。
連絡事項などは必要に応じてメッセージで共有し合うくらいで、無理なく助け合える距離感が心地よく感じます。
小規模校の注意点:廃校・統合のリスクも視野に
小規模小学校には多くの魅力がありますが、将来的に廃校や他校との統合になる可能性がある点は、あらかじめ知っておきたいポイントです。
特に地方や人口の少ない地域では、児童数の減少により、
といったケースもあります。
最近では、統合後も少人数教育を継続したり、新しい設備が導入されたりする例も多く、必ずしもデメリットとは限りません。統合によって、学びの場が広がることもあります。
我が家も“統廃合危機”に直面しました
実はわが家も、まさかの入学1年目で統廃合の話が浮上し、驚きました。
でもその後、新1年生がたくさん入学してくれて、今も息子は元気に学校に通えています(笑)
将来的にまた変化があるかもしれませんが、私たちはあまり心配しすぎず、「今この学校の環境が子どもに合っているかどうか」を大切にして選びました。
「統合の可能性があると分かっていても入学させた理由」は、ただ一つ、“低学年のうちに、落ち着いた環境で安心して学校生活を送ってほしかったから”です。
目の前の1〜2年の安心が、子どもにとってどれほど大きな意味を持つか。
そう考えると、統廃合のリスクも受け入れられると思えました。
さいごに
1年間を通して感じたのは、「小規模校=劣っている」ではないということです。
勉強の進度も、友だち関係も、行事も、どれも子どもにとっては“良い意味で濃くて深い”経験になっていました。
もちろん、大規模校にしかない魅力もありますが、「うちの子にはこの環境が合っていた」と心から思える1年でした。
とはいえ、韓国では小規模な小学校は全く人気がありません(苦笑)。
教育熱が高く、競争の激しい社会に送り出すためには、小さい頃から多くの経験をさせたい――そんな親心が大きな理由でしょう。
そのため、マンモス校でたくさんの子どもたちと触れ合うことが、良い選択肢と考えられるのかもしれません。
一方で、小規模校は個性的なプログラムが充実していることが多く、夏休みも朝から夕方まで通えるようなスケジュールが組めるのは本当に最高!
子どもたちも小さな学校をとても気に入っています。
韓国の小学校の話なので、直接参考になるかは分かりませんが、もし「小規模校に入れていいのか…」と迷っている保護者の方がいらっしゃれば、この体験が少しでも参考になれば嬉しいです。