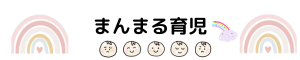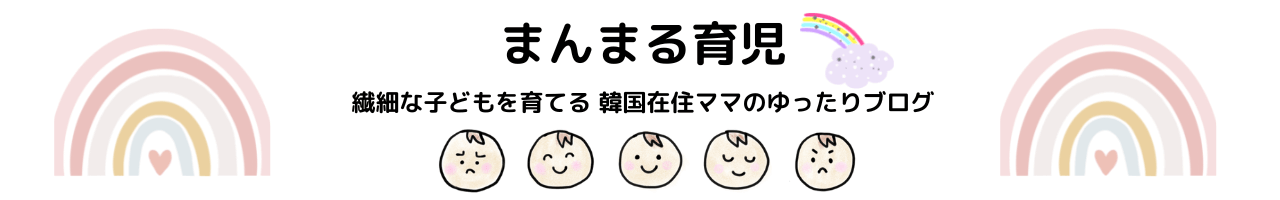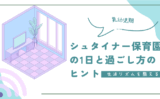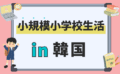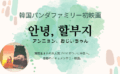今どきの就学前教育って、ちょっとハードル高く感じませんか?
小学校に入る前から、ひらがな・数字・簡単な計算まで身につけておくのが「当たり前」になりつつありますよね。
「勉強させたほうがいいかな…」「遅れたらかわいそうかも」と焦る気持ちもよくわかります。
でも我が家は、“あえて何も教えない”まま、小学校生活を迎えました。
ひらがな(とハングル)も、数字も、時計すら読めなかった息子が、どうやって学校に馴染んでいったのか。
今だから思う、「焦らなくてよかった」と思える日々を振り返ってみます。
うちは“教えない”まま入学
息子が通っていたのは、シュタイナー教育を取り入れた保育園。
そこでは「小学校入学までは読み書きや計算は教えない」という明確な方針がありました。
数字や文字が一切ない教室で過ごしていたので、家庭でもそれに倣い、特別な“お勉強”は一切しないスタイルで過ごしていました。
文字や数字に自然と興味を持つ子もいて、年長になるとお手紙を書いたり読んだりする姿もありましたが、息子はそういうタイプではなく、絵本も「絵を楽しむ派w」。
言葉もややゆっくりめだったので、文字に興味を持つことはほとんどありませんでした。
箸と鉛筆、どっちもまだ早かった?
年長の頃、息子が全く箸を使いたがらず、私は少し焦りを感じていました。
そんなとき、園の先生がこんなふうに教えてくれました。
「箸を上手に使えるようになるのは、指や手首が柔らかく動くようになってからです。無理に教えるより、まずは“手の準備”を育ててあげましょう」
さらに、
「鉛筆を持って書くのも、実はとても複雑な動きなんです。箸が自然に使えるようになり、正しい姿勢が保てるようになってくると、鉛筆も動かせるようになりますよ」
園では、手や指を使う遊び(編み物、粘土遊び、紐通しなど)を通じて、“書くための基礎力”を育てているそうです。
その言葉を信じて、焦らず見守ることに決めました。
そして実際、小学校に入ってから毎日鉛筆を持ち、箸で給食を食べるようになると、驚くほど自然にどちらも正しく使えるようになっていました。
授業についていける?入学直後の様子
入学してすぐ始まった国語の授業。
当然、周りの子たちは読み書きに慣れていて、すらすら書ける子も多くいました。
一方の息子は、見るもの聞くものすべてが初めてで、
黒板の文字をノートに写すのも時間がかかり、毎日とにかくクタクタ。
少しのことで泣いたり怒ったりする日もありましたが、それでも「学校行きたくない」とは言わなかったのが救いでした。
先生が、「焦らなくて大丈夫。今は“練習の時間”だからね」
と毎日声をかけてくださったことが、息子の心の支えになっていたようです。
私も、「書くのが一番遅い…」と落ち込む息子に、
「毎日コツコツやれば、必ずできるようになるよ」と伝え続けました。
学習が遅れても不安にならなかった理由
なんで読み書きを教えなかったことが不安にならなかったかというと、保育園の先生と息子の“心の力”を信じていたから。
息子は、わりと自己肯定感が高いタイプで、何かができなくてもすぐに落ち込むことはなく、こんなふうに言います。
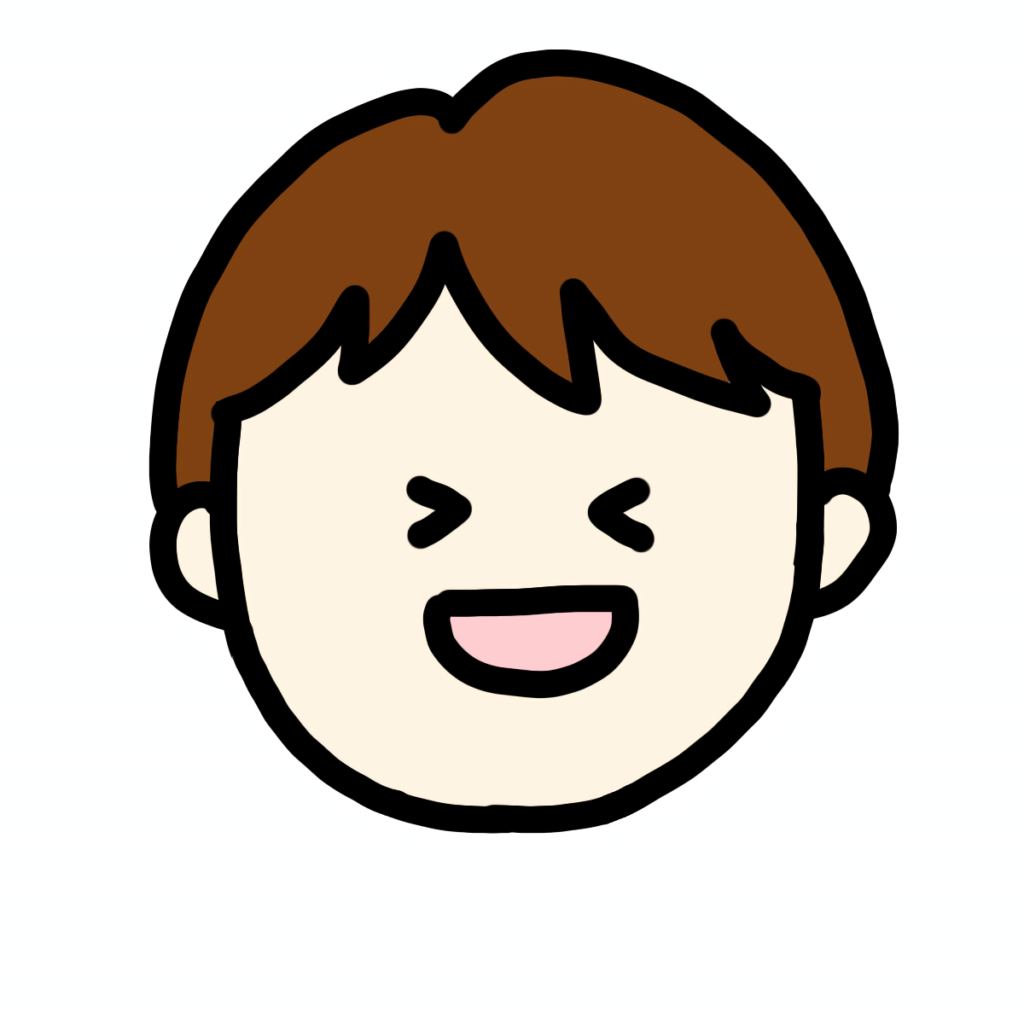
「練習すれば、ぼくもできるようになると思う」
「できないのは、今までやってこなかったから」と冷静に受け止めて、自分のペースで前向きに考えられる。
この“自分を信じる力”があるからこそ、「今できないこと」に振り回されずにすみました。
逆に、もし息子が繊細で傷つきやすく、劣等感を感じやすい性格だったら、
私ももっと早くから先取り教育をしていたかもしれません。
子どもによって性格や気質は本当にさまざま。
だからこそ、「みんながやってるから」「周りと比べて…」ではなく、
“わが子にとって今なにが合っているか”を軸に考えることが、一番大切だと思っています。
先生との面談でわかったこと
1年生の1学期も終わりに近づいたころ、担任の先生との個人面談がありました。
正直、「やっぱり“遅れ”を指摘されるかも…」と少しドキドキしながらのぞんだのですが、
先生は穏やかな口調で、こんなふうにお話してくださいました。
「〇〇くん、とても一生懸命授業に取り組んでいますよ。
周りの子に比べて書くスピードはゆっくりですが、
集中力がありますし、話を聞く力もしっかりしています」
まずはそう言ってもらえて、親としてちょっとホッとしました。
でも、やはり次に続いたのは、
「ご家庭では、文字の練習や読みの練習など、何か取り組んでいらっしゃいますか?」
という確認。
さらに、
「入学後に学ぶことになってはいますが、やはり今は多くの子がすでに就学前に文字や数字に慣れてきています。
学校でも一から教えるつもりではありますが、授業のテンポや理解度を考えると、
家庭でのサポートはどうしても必要になりますね」
——という、ちょっと現実的なお話もありました。
建前と本音の違いって、こういうところで感じますよね(笑)
公立の小学校でも「ひらがなは入学後に一から教えます」とは言うけれど、
実際には“もうできてる前提”でサクサク進む場面もけっこうあるのが正直なところ。
もちろん、まったくできないからといってダメということはありません。
うちの息子のように、スタートはゆっくりでも、ちゃんと書けるようになります。ただちょっと、時間がかかるだけ。
だから、「今できない=ずっとできない」じゃないんですよね。
わが家の学習ルールは15分だけ
そんなわけで、わが家でも1日15分だけ、家庭学習の時間をつくるようになりました。
といっても、いわゆる“ドリル”や“がっつり机に向かう”ようなものではなく、
という、とってもゆるくてシンプルなスタイル。
本人がやりたくない日もあるし、「面倒くさい〜」と逃げようとすることもありますが(笑)、
「約束したから、今日はちゃんとやろうね」
「やったらすぐ自由時間だから!」
と声をかけて、“勉強=嫌なもの”にならないように気をつけています。
家ではのんびりしたい息子にとっては、これくらいがちょうどいいみたいです。
「できるようになった」より「続けている」ことを大切に
少しずつ読み書きができるようになってきた息子。
でも私は、「上手に書けた」ことよりも、「毎日少しずつでも続けられている」ことの方が、よっぽど大事だなと思っています。
周りより遅くてもいい。
焦らなくても、その子なりのペースで“できる日”は必ず来る。
先生との面談では現実的な面にも触れましたが、同時に「おうちのサポート次第で、〇〇くんはどんどん伸びますよ」とも言っていただけて、今は前向きに取り組めています。
早くより“育ちの土台”を
我が家が、いわゆる「早めの読み書き練習」をしなかった一番の理由は、学力よりももっと先に育てたいことがあったからです。
それは、
そういった、“生きる力”のようなもの。
小学校に入って感じたのは、この部分がしっかりしていれば、学習はあとからでもちゃんとついてくるということです。
たとえば、先生の話をちゃんと聞ける力や、お友だちと助け合える気持ち、失敗してもめげないメンタル。
どれも、読み書きよりずっと早くから、遊びや生活の中で育ってきたように思います。
子どもの“学びスイッチ”は3人いれば3通り
まわりと比べて、読み書きが遅いと「うちの子だけ取り残されるかも…」と不安になること、ありますよね。
でも、それって「まだ慣れていないだけ」だったり、「今は他のことに夢中なだけ」ということも多いんです。
学びのスイッチは、子どもによって入るタイミングが本当にさまざま。
早くできることにももちろん意味はあるけれど、遅く始めたからこそ「楽しい!」「もっと知りたい!」と感じて、深く学べる子もいます。
最近は、ひらがなやカタカナ、簡単な計算などを“できていて当たり前”のような雰囲気もありますが、
周りに合わせるよりも大切なのは、“わが子にとってちょうどいいタイミング”を見極めること。
早く始めるのが合っている子もいれば、じっくり型の子もいます。
どちらが正解ということではなく、その子自身のリズムに合った関わり方をしてあげることが、いちばんの近道なんじゃないかなと思っています。
さいごに
2年生になった今、息子は少しずつ「丁寧に書くこと」の大切さに気づき始めています。
新しい担任の先生からは「文字は、人に読んでもらえてこそ意味がある」と教わり、本人の中でも意識が変わってきたようです。
最初は書けるだけで精一杯だった息子も、少しずつ“伝えるための文字”に向き合うようになり、成長を感じる場面が増えてきました。
1年生ではゆるやかだったペースも、学年が上がれば自然と求められることも増えます。
でも、その変化の中でこそ、子どもはたくましく育っていくのだと実感しています。
振り返ってみると、就学前に無理に教えこまなかったことが、我が家にとっては正解でした。
必要なときがくれば、子どもはちゃんと学ぼうとします。
「まだできない」は「これから伸びるサイン」なんですよね。
焦らず、信じて、見守る。
それが子どもにとって、いちばんのサポートになるのかもしれません。
わが家の体験が、同じように不安を感じている方の小さなヒントになれば嬉しいです。