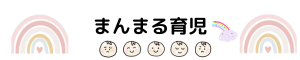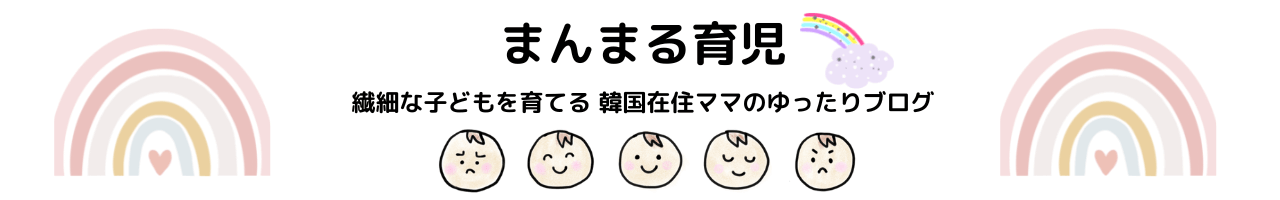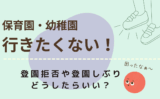〜シュタイナー園の1日から学ぶ、心と体にやさしい時間の重ね方〜
「生活リズムが大事」とよく耳にしますが、実際にどんな1日を過ごせばよいのか、明確なイメージがわかないこともありますよね。
私の息子が通っているシュタイナー保育園では、1日の流れをとても大切にしており、特別なイベントよりも、同じことを繰り返す毎日のリズムそのものが子どもを育てると考えています。
今回は、シュタイナー園での過ごし方をもとに、家庭でも参考にできる「暮らしのリズム」のヒントをお届けします。
生活リズムを整えることで得られること
生活リズムを整えるために大切なのは、「睡眠」「食事」「遊び」の3つ。
きちんとした食事をして、おもいきり遊び、質の良い睡眠をたっぷりとりましょう。
一般的に、生活リズムを整えることのメリットを挙げてみます。
親がこどものリズムに合わせた生活をすることはなかなか難しいかもしれませんが、幼児期は生活リズムを整えやすい大切な時期だと思って、親自身の生活も見直してみてはいかがでしょうか。
朝:起きる・食べる・始める

朝は決まった時間に起きることからスタート。
我が家では、息子が起きる少し前にカーテンを開けて太陽の光で自然に目覚めるようにしています。
朝ごはんはしっかりと。
園でも家庭でも、落ち着いた静かな環境で「食べること」に集中する時間をつくります。
先生は大きな声で注意をせず、そっと促すだけ。子どもたちが安心して食事に向き合える空気を大切にしているのが印象的です。
午前:自由に遊び、集中する時間へ
9:00〜 自由遊び

登園後は、木の実や布など自然素材のおもちゃで自由に遊びます。
決まった遊び方がないからこそ、子どもたちの想像力がどんどん広がっていくのがシュタイナー園の魅力。
10:00〜 お片づけ
鈴の音と先生の歌で、片づけの時間へ。
縦割り保育のシュタイナー園では、2歳から6歳までの子どもたちが一緒に生活します。
小さい子たちは簡単にできるおもちゃの片付けをし、大きい子たちは、重いものや大きいものを運びます。
縦割り保育の中で、年齢に応じた役割を自然に果たす関わり合いも育まれます。
10:15〜 リズム遊び(ライゲン)
輪になって、季節の歌や手遊び歌で心を集中させる時間。
毎日繰り返し歌うことで、子どもはリズム感と想像力を育み、親子でも楽しめる遊びになります。
簡単な手遊び歌や童謡などを事前に覚えておくと、子どもが一生懸命マネしようとします。
季節が変わるときに新しい歌にかえるのも良いですね。子どもは自然に季節も認識しやすくなります。
子どもたちは動画やCDよりも、お母さんやお父さんの声の方が遥かに嬉しいはず。とても良いコミュニケーションの時間にもなりますよ。
10:45〜 おやつと外遊び
おやつは、曜日ごとに決まった素朴なメニュー(例:月はおかゆ、金はりんごなど)。
家庭でも「曜日ごとのおやつ」や一緒におやつを作る体験がおすすめです。
家庭では、子どもと一緒におやつを作るのもオススメ。
遊びのひとつとして調理の手伝いをすることで達成感も味わえるし、料理に興味を持ったり、苦手な食べ物を食べるようになったりとメリットが大きいです。
11:00【外遊び】

その後は公園まで散歩をして、自然の中でのびのびと遊ぶ時間。雨の日も雪の日も外へ出かけます。
自由に遊ぶ時間なので、決められた場所のなかで子どもたちは体を動かし、感覚を働かせて遊びます。
公園の遊具で遊ぶことはほとんどなく、友だちと鬼ごっこをしたり、木の実や木の枝を集めて何かを作ったり、虫を見つけて遊んだりします。
また、息子の通う園では、春と秋には週に一度の山歩きもあり、10時〜13時まで自然の中でお弁当を食べながら過ごします。
12:00〜 気持ちを落ち着かせる時間

園に戻ったら、部屋を薄暗くしてローソクを灯し、静かな時間へ。
ラベンダーのアロマオイルでのマッサージや素話(絵本を使わず声だけで語るお話)で、外遊びの高揚感をゆっくり沈めます。
このような「緩やかな切り替え」が、子どもたちの集中力と心の静けさを育ててくれるのです。
先生の小さなお話は、絵本などを使わず、身振り手振りと声だけでお話を伝えるシンプルな手法の「素話」。あまり感情を出さないように淡々と伝えるようにします。
そうすることで、子どもたちは自然と集中力や聞く力がつき、頭のなかでたくさん想像力を働かせます。
ここまでの過ごし方をみてみると、シュタイナー園では、「緊張と緩和(集中する時間と自由な時間)」が自然と交互になるような時間割になっていて、リズムのある生活を生んでいることが分かりますね。
12:30〜 昼食
食前には感謝のお祈りをします。家庭なら、「いただきます」で十分です。
園では給食専任スタッフがオーガニック素材を使って調理。味付けはシンプルですが、出汁が美味しく薄味でもとても美味しい。
雑穀米に、野菜・海藻・発酵食品(韓国ではキムチ)など、体にやさしい和食/韓食スタイルのメニューです。
家庭でも「感謝して食べる」習慣を大切にできたらいいですね。
13:30〜 お昼寝の時間
シュタイナー園では、パジャマに着替えます。
給食後、歯磨きをしてパジャマに着替えたら、お昼寝へ。
2歳児でも「自分で着替える」を大事にして、先生はすぐに手助けをせず、そっと見守ります。
服が前後ろ反対でも注意をしたりしません。先ずは、「自分でやる」という自立心を大事にしたいですね。
ライアー(ドイツの竪琴)の音色や素話を聴きながら、体と心を休める静かな時間。
息子は眠れないタイプですが、布団の中で静かに横になっています。
家庭でもこの時間帯は、活発な遊びを控えて「静かな時間」に切り替える工夫が効果的です。
ライアーは、シュタイナー教育で使う心地よい音色が出る小型のハープのような形をした楽器ですが、弾き方などもハープとは異なります。映画『千と千尋の神隠し』の主題歌「いつも何度でも」で使われている楽器ですね。
息子の通う園ではお昼寝は年長さんまで必須です。
敏感な息子は園で眠れませんが、布団で横になっているそうです。年齢が上がると時々眠れない子どももいるようですが、家庭でもお昼寝の時間帯は活動的な遊びではなく、ゆったりと過ごすようにしましょう。
15:00〜 午後のおやつと自由遊び

午後のおやつは、蒸かし芋・果物・お餅・手作りパンなど腹持ちの良いものが中心。
薄味で、素材の味を楽しむメニューが多く、甘さ控えめのジャムやはちみつを添えたパンが人気です。
素材の味が良ければ美味しく食べれ、子どもたちはシンプルな味を好むようになります。
家庭でおやつを作るときも、玄米、はと麦、ライ麦、小麦、米粉など様々な穀物を使うと良いでしょう。こちらでは、小麦粉の代わりによく米粉を使います。
おやつのあとは、お迎えまでの自由遊び。
にじみ絵・クレヨン画・手仕事など、静かで創造的な活動を年齢に合わせて楽しみます。
夜:スムーズな眠りのために
夜の眠りに向かうためには、毎晩同じ流れを繰り返す“就寝ルーティン”を整えることがカギ。
例:お風呂 → 夕食 → 歯みがき → トイレ → 寝室へ → 絵本やマッサージ → 就寝
たとえば、このような順で流れるように時間を過ごし、電気を消して静かな環境を整えて眠りに就くようにします。
テレビ視聴は、就寝時刻が遅くなったり睡眠時間が短くなりやすいので、夕方以降は、テレビを見せない方がスムーズに進みます。
夜になるにつれて、カーテンを閉めたり部屋の明かりを暗めに調節したりすると、子どもたちの体は寝る準備を始めるのでオススメ。時間と順番を毎日繰り返すことで、子どもは「もう寝る時間だ」と自然に意識できるようになります。
保育園と同じく、我が家もヴェレダのラベンダーオイルを使用。
シュタイナーが設立に関わったブランドだと知ってから、ますます親しみがわいています。
さいごに|暮らしに“リズム”があるということ
成長著しい幼児期において、体の発育と心の安定のために「リズムある生活」はとても大切です。
とはいえ、完璧に時間通りに…と気負わなくても、体内時計と季節の流れに合わせて、自然にそうなっていくように整えていくことが理想だと感じています。
シュタイナー園では、1日・1週間・1年それぞれにリズムがあり、家庭でも「〇曜日は〇〇を食べる」「季節ごとの行事を大切にする」など、暮らしにやさしい“くり返し”を取り入れるだけで、子どもも安心感を得やすくなります。
記念日や季節の行事を家族で楽しむことは、子どもの中に「心の季節」をつくる大切な体験にもなるはずです。
シンプルだけど本質的。
小学校に上がるまでは特に、繰り返しの力を信じて「リズムのある暮らし」を意識してみるのはいかがでしょうか。