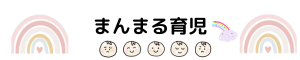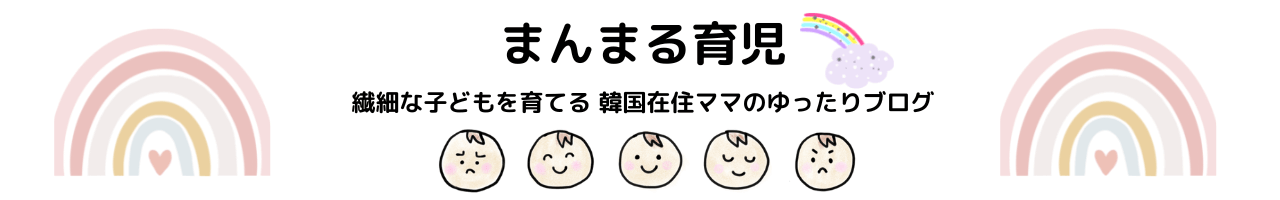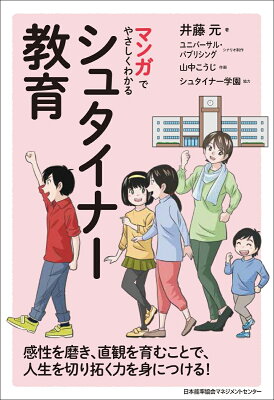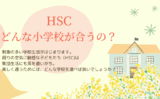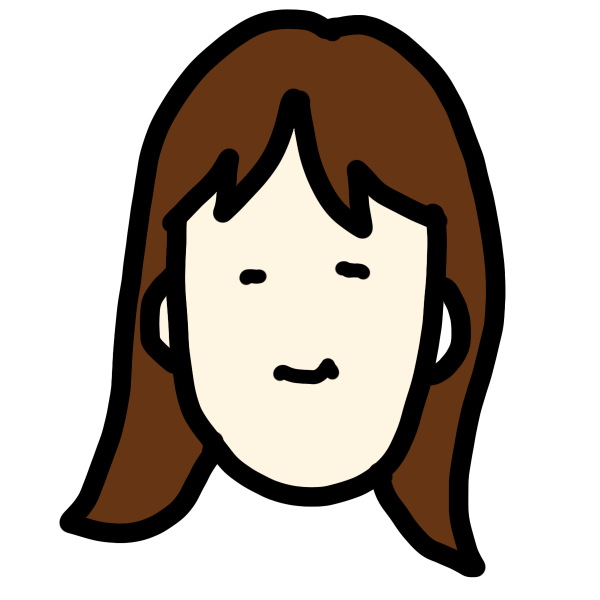
何かお悩みはありますか?
来年はいよいよ、HSC(ひといちばい敏感な子)の息子が小学校に入学する年です。
私たちの最大の関心事はただひとつ── 「どんな学校なら無理なく通えるのか?」。
保育園の面談でも、先生から「繊細なお子さんは大規模校だと慣れるまで大変かもしれません。小規模校やシュタイナー校のような環境のほうが合うと思いますよ」とアドバイスをいただきました。
この言葉に背中を押され、少しずつ候補を調べ始めることに。
結果として見えてきたのは、学区内の公立校だけでなく、オルタナティブスクールや学区外の小規模校など、意外に多様な選択肢があるということでした。
候補に挙がった4つの小学校
① 学区内の中規模公立小学校
もっとも身近で通いやすい選択肢。
地域とのつながりがあるのは安心ですが、保育園と比べると児童数が多く、
HSCの息子には刺激が強いかもしれないと感じました。
一方で、授業以外に運動や遊びの時間も多く「思ったより楽しめそう」という印象もあり、
親としては最後まで悩んだ選択肢です。
② シュタイナー小学校(オルタナティブ教育)
今の保育園がシュタイナー園なので、同じ教育理念で育てられるのは魅力的。
ただし学費が高額で、国の補助も少なく、卒業資格が認定されない場合もあるのが現実。
さらに、もし途中で公立校に転校した場合、学力の進度差で息子が苦労するのではないかという不安もありました。
③ 多文化小学校
外国籍の子が多く、多様な文化に触れられる点は魅力。
一方で韓国語環境が弱くなる懸念があり、息子の言語面での成長に影響があるかもしれません。
また、HSCの子にとって「文化の違いによる環境変化」がどんな負担になるかも、慎重に考える必要があると感じました。
④ 学区外の小規模公立小学校(最有力候補)
徒歩圏内にあり、少人数でアットホームな雰囲気。
電話応対も丁寧で第一印象がとてもよく、「家族のように見守ってくれる」学校になるかもしれないと期待できました。
ただし、学区外からの入学には「指定校変更」の申請が必要で、自治体によっては抽選や人数制限があると知り、制度面での確認も重要だと学びました。

シュタイナー教育を手放す決断
保育園の先生からも勧められたシュタイナー教育。
私自身も魅力を感じていましたが、費用面・制度面での負担を考え、今回は手放すことにしました。
電子黒板やデジタル教材を使う公立校は、息子にとってギャップがあるかもしれません。
それでも、「現実的に無理なく通える」ことを第一に考え、一般の学校を選ぶ覚悟をしました。
まとめ:HSCの子にとって大切なのは“環境”

保育園の面談で先生から言われた、
「繊細なお子さんは、大規模校では慣れるまで大変かもしれません。小さな学校の方が合うと思いますよ」
という言葉が、今でも心に残っています。
その一言で「学校は学区だけではなく、いくつも選択肢がある」と気づくことができました。
結局のところ、HSCの息子にとって一番大切なのは、安心して毎日を過ごせる環境です。
学力やカリキュラムよりも、「ここなら大丈夫」と思える場所を選ぶことが、親としてできる最大のサポートだと感じています。
これから先も、先生や友だちとの相性で悩むことはあるかもしれません。
でも、そのたびに「この子に合う環境」を柔軟に探していければいい。
小学校は「選べる時代」。
今回の経験を通じて、選択肢の幅広さと、先生とのあたたかいやりとりが、私たち親子にとって大きな支えになりました。