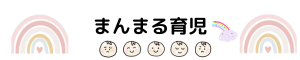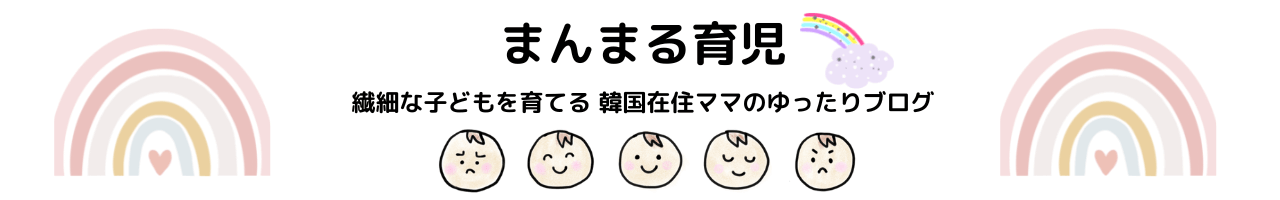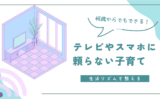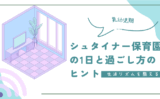~非認知能力が最も伸びる0〜6歳の乳幼児期に、どんな環境を選ぶか~
進路や教育方針に悩む親御さんにとって、この問いは一度は立ち止まる大きなテーマかもしれません。
学習系の園、英語教育、早期教育…。選択肢が豊富な今、つい見落としがちなのが、「非認知能力」という目に見えない“人としての力”です。
自己肯定感、共感力、集中力、失敗してもくじけない心。
こうした力は、知識とは違い、幼児期の環境や大人との関わり方で大きく育つと言われています。
この記事では、韓国のシュタイナー園に通わせた私自身の経験も交えながら、
非認知能力とは? 幼児期にこそ育みたい「目に見えない力」
「非認知能力」とは、IQやテストでは測れない、人間の内面的な力を指します。
これらはまさに、“人間らしく生きる力”とも言えます。
しかもこれらの力は、就学前の0〜6歳の時期にこそ大きく伸びるのです。
なぜ非認知能力がこれからの社会で重要なのか?
テクノロジーが進化し、AIやロボットが私たちの生活や仕事に深く関わる時代。
情報処理や計算、ルーティン作業など、「正解のある仕事」はどんどん機械に置き換えられていきます。
では、人間にしかできないこととは何でしょうか?
それは、
といった、非認知能力に基づく“人間らしい思考と行動”です。
たとえば、ある人が落ち込んでいるときに、そっと声をかけたり、空気を読んで話題を変えたりする。
あるいは、多様な人と協力して問題を解決する。
これらはマニュアル通りにはいかない、人間だからこそできる対応です。
こうした力こそが、今後の社会でより重視され、仕事だけでなく人間関係や自己実現の面でも大きな価値を持ちます。
教育現場も注目!非認知能力の育成が大切な理由
文部科学省がまとめた「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」では、以下のような育ちが大切にされています:
こうした経験を積み重ねることで、子どもは「自分って大丈夫」と思えるようになります。
これらはすべて、非認知能力の要素です。
実際、文部科学省は資料の中で、非認知能力の育成を目標として明確に掲げています。
(参考)文部科学省公式PDFはこちら
非認知能力をより育てやすい園を選ぶなら?
多くの園では「英語教育」「知育教材」「運動プログラム」など、学習面のカリキュラムが注目されがちですが、非認知能力の視点から見ると、重視すべきポイントは少し異なります。
子どもの“心の力”を育てるには、安心できる環境、自由な表現、信頼関係がとても重要です。以下のような観点で園を見てみると、非認知能力が育ちやすいかどうかのヒントになります。
園見学で見ておきたいポイント:
- 自由な遊び時間があるか
→ やらされるのではなく、自ら選んで取り組める環境か。 - 先生が命令型でなく対話的か
→ 「どうしたい?」「一緒にやろうか」と子どもに寄り添っているか。 - 過程を大切にしているか
→ 成果や“できた・できない”ではなく、挑戦そのものを肯定しているか。 - 想像力を育てる素材やおもちゃか
→ シンプルな形や自然素材が中心になっているか。 - 生活にリズムがあるか
→ 毎日の流れに“安心できる繰り返し”があるか。
こうした要素がある園では、子どもが自分らしく過ごし、感情を表現し、社会性や自律心を自然に身につけやすいとされています。
大切なのは、「早くできるようにする」よりも、「ゆっくりでも、自分らしく育っていけること」。
園選びは、そうした子どもの“育ちの質”を支える大きな選択です。
園で育む非認知能力:具体的な遊び例
非認知能力は、「自由な遊び」や「日常の活動」から自然と育まれます。以下は代表的な例です:
◎ごっこ遊び(ままごと、店屋さん)
育つ力:共感力・社会性
◎木製積み木やブロック遊び
育つ力:空間認識・集中力・創造性
◎料理や掃除の手伝い
育つ力:自主性・模倣力・自信
◎自然の中での探検ごっこ
育つ力:好奇心・自己判断力
◎手仕事(毛糸遊び・布人形づくり)
育つ力:忍耐力・丁寧さ・自己表現
オルタナティブ教育という選択肢
一般的な園とは異なる教育スタイルを取り入れた「オルタナティブ教育」。
子どもの個性や成長ペースを尊重し、非認知能力を大切にした実践が行われています。
代表的な教育法:
このような園では知識の詰め込みよりも、“自分らしさ”を育てるアプローチが特徴です。
我が家の場合:シュタイナー保育園に通った息子
私の息子は韓国のシュタイナー園に通っていました。
教室には木の香りと先生のやさしい声が広がり、おもちゃはすべて自然素材。
先生は「教える人」ではなく、「手本となる大人」として日々の暮らしを共にしてくれました。
息子は次第に──
テレビやスマホの制限、食のこだわりなど保護者にも覚悟が必要でしたが、“その子らしく育つための力”を育む場所としては、理想的だったと今でも感じています。
参考にした動画・書籍
子育てや教育方針について考えるときに、科学的な視点からの情報もとても役立ちます。
私が実際に視聴し、参考になった動画はこちらです:
これらの動画に出演している中室牧子先生の著書も読みましたが、
非認知能力や教育の効果をデータで読み解く内容がとても興味深く、
感覚や雰囲気だけに頼らない、教育の選び方を改めて考えさせられました。
家庭でできる非認知能力の育て方
「非認知能力」は、特別な教育を受けないと育たない…と思われがちですが、実は家庭でのちょっとした関わりの中でも、しっかりと育てていくことができます。保育園や幼稚園だけに任せるのではなく、日々の暮らしの中で“心の力”を育てていくことが大切です。
家庭でできる3つのこと
◎ 習い事で育てるなら:自然体験・プログラミング・スポーツ・音楽・芸術などもおすすめです

さいごに:点数より大切な“その子らしさ”を育てる選択
保育園選びや教育方針に迷ったとき、ぜひ一度立ち止まって思い出してみてください。
この子がどんな大人になってほしいか?
早く字を覚えることより、“自分で考えて行動できる人”になれるかどうか。
非認知能力を育てることは、テストの点数には表れません。
でも、それは一生の「生きる力」になるはずです。